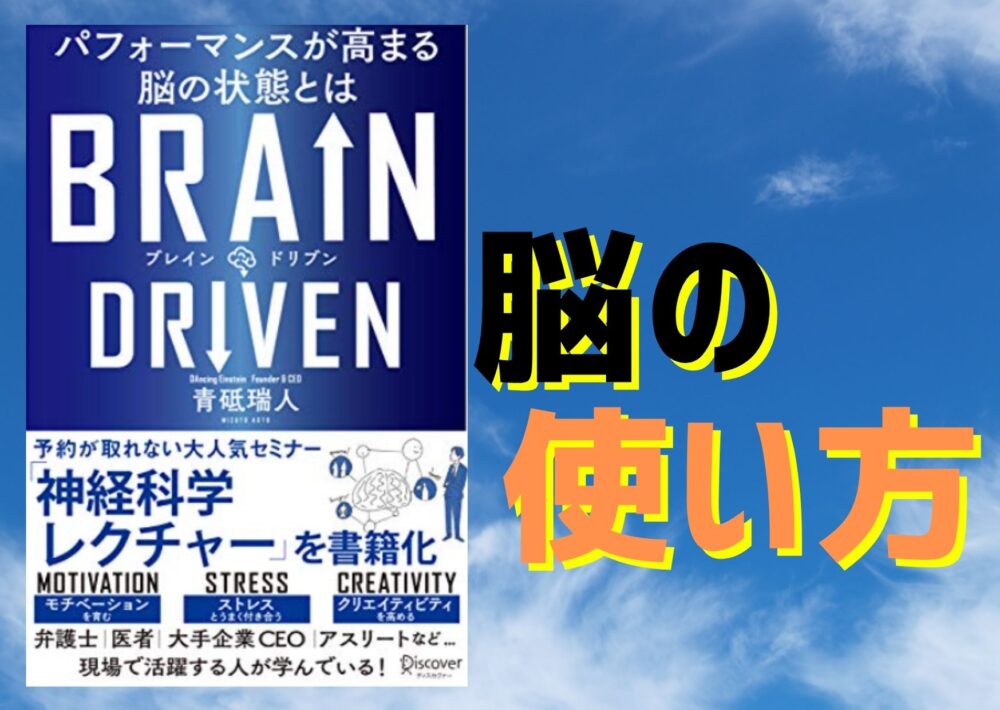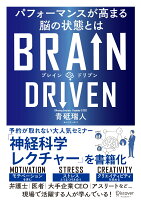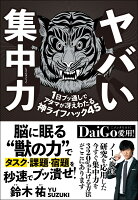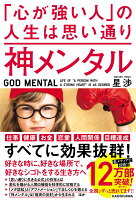この記事で分かること
- モチベーションのメカニズムが分かる
- ストレスの必要性が分かる
- クリエイティビティの育み方が分かる
電子書籍のサブスクKindle Unlimitedの無料体験でも読めるので、フルで読みたい方はどうぞ。

それではいってみましょう。
もくじ
『BRAINDRIVEN(ブレインドリブン)』の基本情報【神経科学レクチャー】
まずは『BRAINDRIVEN』の基本情報について見ていきます。
書名 :BRAIN DRIVEN パフォーマンスが高まる脳の状態とは
著者 :青砥瑞人
出版月:2020/9/25
出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
定価 :¥2,420 (税込)
著者である青砥瑞人さんのプロフィールはコチラです。
DAncing Einstein Founder & CEO。日本の高校を中退。その後、米国大学UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の神経科学学部を飛び級卒業。脳の知見を、医学だけでなく、そして研究室だけに閉じず、現場に寄り添い、人の成長やWell‐beingに応用する応用神経科学の日本パイオニア。また、AI技術も駆使し、NeuroEdTech/NeuroHRTechという新分野も開拓。同分野にて、いくつもの特許を保有する「ニューロベース発明家」の顔ももつ。人の成長とWell‐beingに新しい世界を創造すべく、2014年に株式会社DAncing Einsteinを創設。
-Amazon著者情報より抜粋-
脳を学び、神経科学を応用する時代を迎えました。
- 脳の中で起こっていることを解き明かし(WHAT)
- なぜそうなるのかを理解すれば(WHY)
- 高パフォーマンスな自分を創り出せる(HOW)

『BRAINDRIVEN(ブレインドリブン)』の要約【脳の使い方を学ぶ】

それでは、『BRAIN DRIVEN(ブレインドリブン)』の内容を3つのパートに分けて要約していきます。
- モチベーションのメカニズム
- ストレスの必要性
- クリエイティビティを育む
順番に見ていきましょう。
要約①:モチベーションのメカニズム
1) モチベーションを線で考える
モチベーションを捉えるうえでまず必要なのは、
- モチベーション単体(点)で考えるのではなく
- 脳の報酬回路システム(線)で考える必要がある
ということ。
脳の報酬回路は、「生存のためのモチベーション」を優先します。
呼吸や体温が乱れている状態で、仕事や学習のモチベーションが上がるわけありません。
モチベーションを高めたいなら、睡眠や生活リズムの質を高めるのが第一と言えます。
生活リズムの面でモチベーションに影響を与えやすいのが「セロトニン」という神経伝達物質です。
朝の太陽を浴びて大量のセロトニンをつくると、夜の良い睡眠につながります。
2) ドーパミンとノルアドレナリンが必要
モチベーションを考えるうえで不可欠なのが、ドーパミンとノルアドレナリンです。
- ドーパミン
→好奇心など「何かをやってみたい」と思ってる時に出やすい - ノルアドレナリン
→嫌い・大変・避けたいと思う時に出やすい
モチベーションが高い状態とは、
- ドーパミンが出ている状態を前提として
- ノルアドレナリンも適度に出ている
そんな状態が理想的と言われています。

初期の学びや無知の状態にはドーパミンだけでなんとかなりますが長続きしないのが特徴です。

「困難さ」でノルアドレナリンを出すことも、モチベーションを高めるのに重要なのです。
3) ド-パミンを促す4つの刺激
ドーパミンの効能をうまく自分のものにするには、「どんな時にドーパミンが出るのか」を認知しておくと助けになります。
刺激①:SEEK
- おいしいかもしれない
- 楽しいかもしれない
SEEKは、「追い求める」「探求する」といった心模様です。
経験していないことも「快」の期待があるとSEEKの対象になります。
刺激②:WANT
シンプルに「欲しい!」という心境です。
SEEKと似てますが、WANTは「学習済みの快」であること。
自分の中で何が良いのか分かってる刺激に対する反応です。
刺激③:LIKE
これは好きだ!という感覚がドーパミンを誘発します。
カンタンかもしれませんが、人は自分の「好き」を認識できてないことも多いそうです。
自分の中の「ささやかな好き」にも注意を向けると、些細なことでも快を感じてモチベーションを高めやすくなります。
刺激④:期待値、予測値差分
要するに「ギャップ」ですね。
- 毎月もらえる30万円の給料と
- 臨時収入でもらった30万円
同じ30万円でも期待値とのギャップが大きいのは後者です。
予想外の報酬はドーパミンを誘発します。

要約②:ストレスの必要性
1) ストレスの3つの役割
「ストレス」と言うと、一般的には”ない方がいいもの”と考えられがちですが、人間の脳はストレスによってパフォーマンスが上がることもあります。
本書では、ストレスには3つの役割があると述べています。
伝える力
受け取った情報がどのような種類のものかを伝える役割です。
例えばナイフを持った怪しい人に不用意に近づいたら刺される可能性があります。
そのようなアラートを脳に伝えられるのはストレス反応のひとつです。
記憶力
ストレスによって記憶定着効率が高まり、学習効果が上がります。


BRAIN DRIVEN CHAPTER2より引用
丸の数はさておき、「3秒で数えてください」というプレッシャーが集中力を高めてくれたはずです。
直感力
脳の中で「何かおかしい」「ヤバいぞ」という感覚的・情動的なアラートもストレス反応の一種です。
記憶痕跡化され、推測が立てられるので、その感覚によって「やめておこう」という判断が瞬時に可能になります。
今でこそ安全な日本ですが、太古の昔は外に出れば猛獣に遭遇する危険と隣り合わせでした。
その意味では、ストレスは人間が生存確率を高めるために発達した重要な機能と言えます。
2) 避けるべきストレス
適切なストレスは、人間のパフォーマンスを高めてくれる一方、避けたほうがいいストレスもあります。
過剰なストレス
ストレスが過剰になると頭が真っ白の「思考停止」状態になります。
自分は詐欺には引っかからないと言ってる人も過剰なストレスを与えられると、判断力が失われお金を振り込んじゃうわけです。
とはいえ、どのレベルが過剰なのかは人によってさまざま。
そのため、自分がどのような状況でストレスを感じるかという「メタ認知」が重要になってきます。
慢性的なストレス
- 嫌なことを何度も思い出す
- ストレスを感じる人が常に近くにいる
そんな状況です。
ストレスでコルチゾールが出続けている状態は、細胞を萎縮させうつ病などを誘発します。
慢性化しないよう、自分が落ち着ける場所やモノを見つけておくのが重要です。
3) ストレスのうまく付き合う3つのヒント
無意識バイアスを外す
先ほど丸を数えた画像をもう一度ご覧ください。何か気になることはありませんか?

BRAIN DRIVEN CHAPTER2より引用

人間の脳は、無意識に「指は5本」と捉えがちです。
自分の価値観に潜む「無意識バイアス」を知っておくと、現実との差分によるストレスを事前に察知できます。
要注意なのが「べき論」です。「~すべき」という言葉が出てきたら自分のバイアスを疑ってみるといいかもしれませんね。
自分を俯瞰してみる
嫌な記憶を繰り返し想起しやすい人は、ネガティブなループを加速させ、どんどん自分の世界に入りがち。
そんなときは、空から眺めるように自分を俯瞰的に捉えると、悩みやネガティブな思考が米粒のように小さく感じられます。
例えば、貧しいことをネガティブに捉えていたとしても、世界に目を向けると日本は超裕福です。
餓死することもなければ適切な医療も受けられます。
自分のストレスを客観視し縮小化させるために「他者との比較」を活用するのも有効なのです。
モヤモヤを受け入れる
新しい学びに際して、なかなか頭に定着してくれずにモヤモヤすることはありませんか?
このモヤモヤがストレスになると「自分には向いてない」と感じて長続きしなくなります。
これは実にもったいないことです。
筋肉が育つときに筋肉痛になるのと同じで、脳が学習しているときはモヤモヤするもの。
この仕組みを理解してモヤモヤに対する認識を変えると、不要なストレスを低減してくれるどころか、学びや成長が加速するはずです。
要約③:クリエイティビティを育む
1) クリエイティビティは「結果」ではなく「プロセス」
そもそもクリエイティビティとは何か?という話です。
- 新しく価値ある何かを生み出した「結果」ではなく
- 想像的な行為をしている「状態」である
著者はそう定義します。
新しい価値を生み出してるのは紛れもなく人間ですが、その過程で脳がどうなっているか。

2) Use it or Lose it
クリエイティビティは先天的な才能に起因するわけではなく、後天的に高めることが可能です。
ただし、クリエイティビティを発揮するには多様な脳機能を総動員する必要があります。
- 脳機能を使えば育まれ
- 使わなければ失われてゆく
クリエイティビティを高めたければ、クリエイティブなことに脳を使い続けるしかないということです。

とはいえ、まだ見ぬ世界を想像できるクリエイティブな脳は、先の見えない現代を積極的に楽しめる脳とも言えます。
3) 意識的な無意識化
クリエイティビティが発揮される始点は「デフォルトモード・ネットワーク」という状態に脳がある時です。
クリエイティビティを発揮するには、意識的にデフォルトモード・ネットワークへ誘導するのが近道ということです。
著者はこれを「意識的な無意識化」と呼んでいます。
無意識化の2つの方法
- 脳に空白をもたらす
→たっぷり思考した後にぼーっとする - 単純作業を味方にする
→情報処理を持て余した脳が勝手に働く
『BRAINDRIVEN(ブレインドリブン)』の感想【脳の使って育てる】
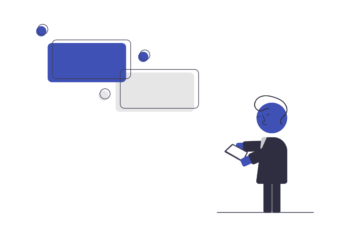
「神経科学」というちょっと難しそうな本ですが、予備知識がない自分でもスラスラ読むことができました。
とても分かりやすく構成されていて、知的好奇心を大いに満たしてくれる1冊です。
まえがきで「本書はハウツー本ではない」と著者は述べています。
HOWは一般化できる答えがないため、自分で創り出すべきという考えです。
自分のHOWを考えるうえで意識したいのが「Use it or Lose it」の原則。

いかなるHOWにしても、脳の機能を「使う」ことを重視していきたいですね。
『BRAINDRIVEN(ブレインドリブン)』とあわせて読みたいオススメ本3選

①『ヤバい集中力』(鈴木祐)
人生の成功にもっとも必要なのは、頭の良さではなく「目先の欲望に負けずに大事なことにコツコツ取り組める能力」であると言われてます。
要するに「集中力」ですね。
人間の心はいつも獣(本能)と調教師(理性)がぶつかり合っています。
獣をうまく乗りこなして高い集中力を発揮する方法を学べる1冊です。

-
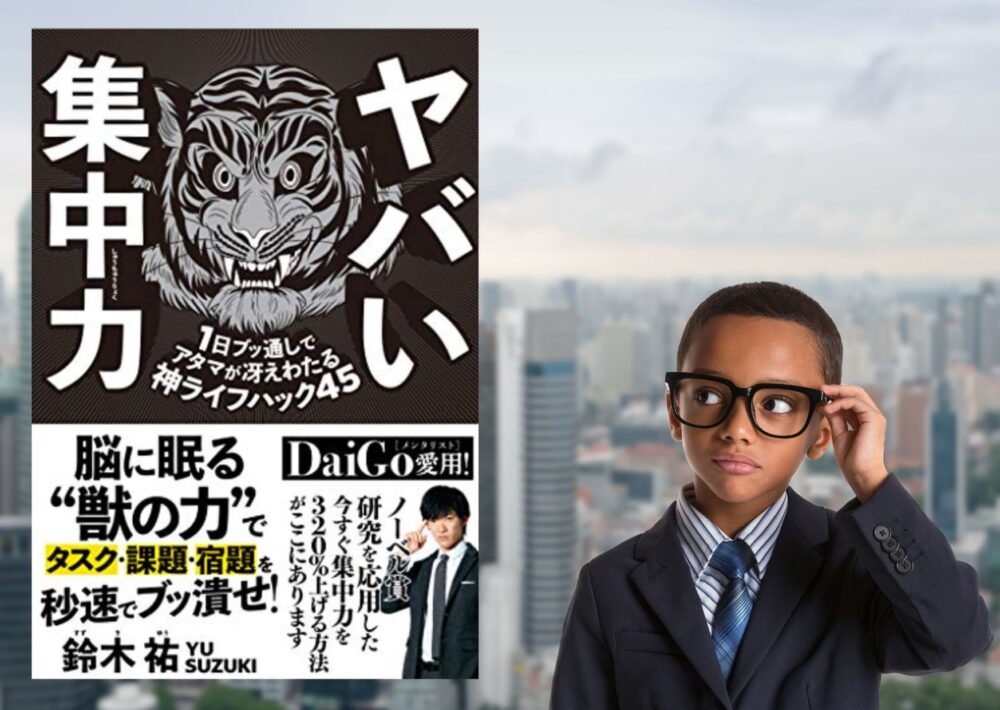
-
『ヤバい集中力』の要約・感想【なぜゲームには集中できるのか?】
②『スゴい早起き』塚本亮
高いパフォーマンスを発揮したいなら朝の時間を活用しない手はありません。

早起き習慣によって人生が変わったという著者が、早起きのメリットを解説しつつ、根性や意思の力に頼らず早起きを続けるコツを伝授してくれます。
-
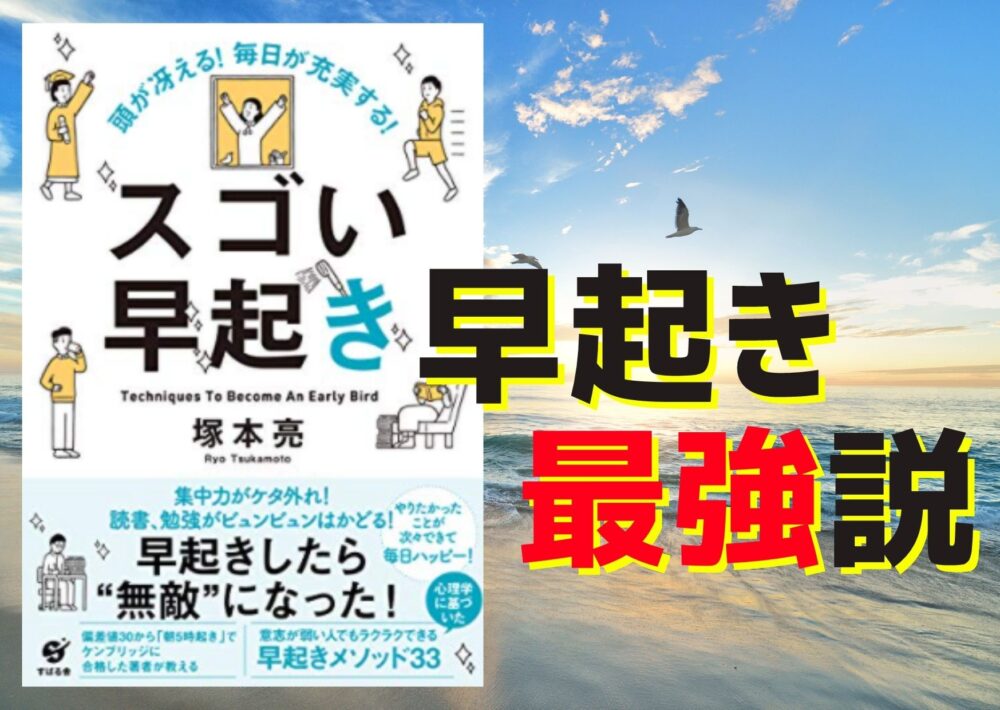
-
『スゴい早起き』の要約・感想まとめ【朝の5分は夜の1時間】
③『神メンタル』(星渉)
現実を変えるためのひとつの真理として「思い通りに生きる公式(現実=目的地×手段×メンタル)」を定義しています。
- いま自分がいる現実も
- これから手にする未来も
全てこの公式で説明できると著者は言います。

-

-
星渉『神メンタル』の要約・感想まとめ【脳のチカラを利用しよう】
まとめ:脳の使い方で人生は良くも悪くもなる

まとめます。
- モチベーションのメカニズム
→ドーパミンとノルアドレナリンが必要 - ストレスの必要性
→適度なストレスは記憶力や直感力を高める - クリエイティビティを育む
→無意識状態がクリエイティビティの始点
新型コロナウイルスで世界は一変し、今後もどうなるか分かりません。
- ネガティブな情報にストレスを溜め続けて生きるのか
- 状況を受け入れつつ新しいチャンスを生み出すか
ちょっとした脳の使い方で、人生は貧しくも豊かにもなりえます。
脳をうまく使うヒントを知りたい方は、いちど本書を手にとってみることをオススメします。
電子書籍のサブスクKindle Unlimitedの無料体験でも読めるので、フルで読みたい方はどうぞ。
今回は以上です。