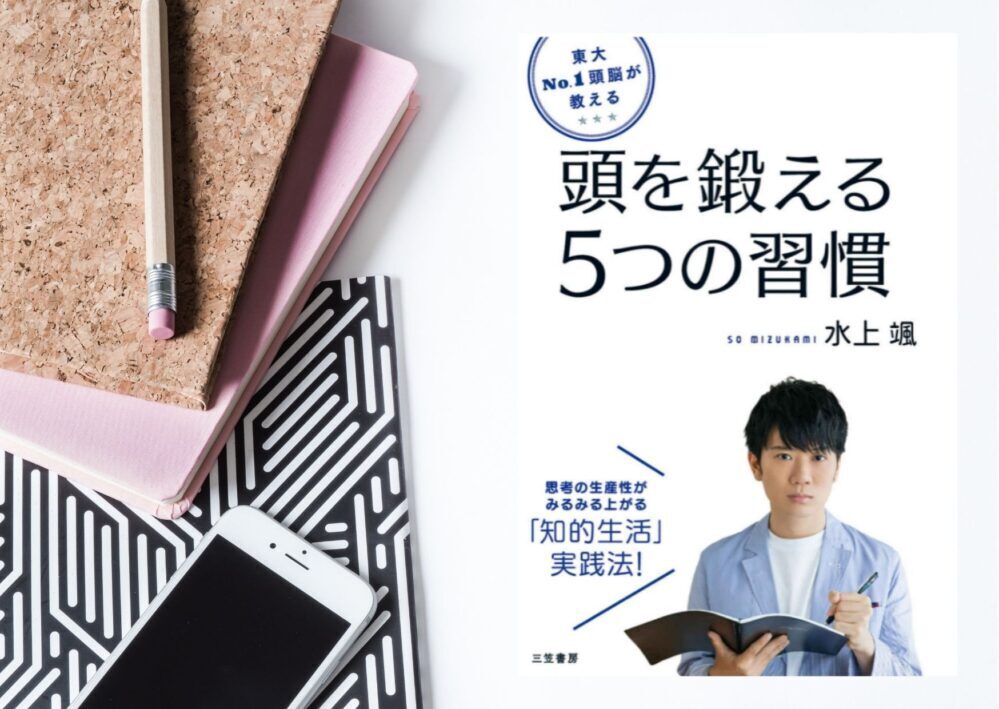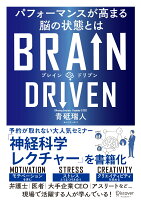この記事で分かること
- 頭を鍛える「勉強」の習慣が分かる
- 頭を鍛える「読書」の習慣が分かる
- 頭を鍛える「時間」の習慣が分かる
電子書籍のサブスクKindle Unlimitedの無料体験でも読めるので、フルで読みたい方はどうぞ。
それでは見ていきましょう。
もくじ
『頭を鍛える5つの習慣』の基本情報【天才は後からつくれる】
まずは『頭を鍛える5つの習慣』の基本情報について見ていきます。
書名 :東大No.1頭脳が教える 頭を鍛える5つの習慣
著者 :水上 颯
出版月:2019/9/6
出版社:三笠書房
定価 :¥1,540 (税込)
著者である水上颯さんのプロフィールはコチラ。
東京大学医学部6年生 1995年山梨県生まれ。2012年、私立開成高等学校在学中に第32回全国高等学校クイズ選手権で優勝。2014年、東京大学理科三類に現役合格。2017年、高い志と異能を持つ若手人材支援を行なう公益財団法人 孫正義育英財団の財団生(1期生)に選ばれる。 TBS系『東大王』に東大王チームとしてレギュラー出演中。その他、クイズ番組を中心にテレビ出演多数。本書が初の著書となる。
-Amazon著者情報より抜粋-
- 現役東大医学部生
- 孫正義育英財団財団生
- 『東大王』リーダー
まさしく「天才」「異才」という印象を抱きますが、著者は『才能ではなく習慣でここまできた』と述べています。
頭を鍛える5つの習慣
- 勉強の習慣
- 読書の習慣
- 記憶の習慣
- 時間の習慣
- アウトプットの習慣
この記事では、そのうち3つの習慣について紹介していきます。
『頭を鍛える5つの習慣』の要約【勉強・読書・時間】

それでは、『頭を鍛える5つの習慣』の内容を3つのパートに分けて要約していきます。
- 頭を鍛える「勉強」の習慣
- 頭を鍛える「読書」の習慣
- 頭を鍛える「時間」の習慣
順番に見ていきましょう。
要約①:頭を鍛える「勉強」の習慣
1) 「小さな目標」をクリアしていく
勉強には、必ず何かしらの目標があるはず。
- 英会話ができるようになる
- 〇〇大学に合格する
- 〇〇の資格を取る
このとき、目標が大きすぎたり遠すぎると、そこまでの道筋が見えにくくなり、途中で行き詰まりかねません。
そうならないためには、大きな目標にそのまま向かうのではなく、小さな目標に分解していくのがオススメ。
- 野球なら○○イニング、○○アウト
- テニスなら○○セット、○○ゲーム
- 登山なら○○合目
勉強に限らず、あらゆる目標は紐解くと小さなチェックポイントに分解できるはずです。
2) 自分に合った勉強法を確立する
勉強は「自分なりのスタイル」を確立することが重要です。
なぜなら、みんながやってるいわゆる”常識的な”スタイルが、必ずしも自分に合ってるとは限らないから。
例えば、授業中にノートをとるのは常識的なスタイルかもしれませんが、もし黒板に書かれた内容をそのままノートに書き写しているだけなら、使っているのは目と手だけで、頭は使ってなかったりします。
であれば、逆にノートは取らずにその時間を「考える」ことに使った方が理解が深まる人もいるかもしれません。
もちろん、頭を使って整理しながらノートをとれる人もいると思いますが、自分もそうとは限りません。
大事なのは、「当たり前」と思われる勉強法も一度疑ってみること。
周りの人がやってるやり方にとらわれず、自分に合った勉強法を探ることが大切です。
3) 勉強を始めるタイミングは「今」が一番
勉強を始めるのに「遅すぎる」ということはありません。
勉強を始めるタイミングは、一番若い「いま」が一番なのです。
なぜなら、先延ばしは長期的に見るとマイナスが大きいから。
人生100年時代が現実になりつつある今、豊かな人生を送るうえで、学びによる「知」こそが大きな財産になると考えられます。
先延ばしは簡単でその場ではラクですが、「あのとき〇〇しておけば・・・」という言葉は絶対使わないようにしたいもの。
もし怠けたい気分になったときは、やがて自分に降りかかるマイナスに思いを至らせると、己を鼓舞することができるはずです。
要約②:頭を鍛える「読書」の習慣
1)「冷めた読み方」で思考力を磨く
本とは「著者の主張をまとめたもの」ですが、著者の主張が必ずしも正しいとは限りません。
どんな本であれ、「これは著者の考えに過ぎない」という冷めた読み方をした方がいいと著者は述べています。

統計やグラフにも注意が必要です。
データが示しているからといって、しっかりしたエビデンスが揃ってるとは限りません。
グラフの見せ方次第で読み手の印象をコントロールするのは、さほど難しいことではないのです。
「冷めた読み方」を身につけるためには、
- あえて自分の意見と違う本を読んでみたり
- 意見が相反する2冊を読んでみたり
するのがオススメです。
2) 「原典」にチャレンジする
名著といわれる本には、内容が難しい本も少なくなりません。
難しい本を読むのははっきり言って大変ですよね。
そこで、もっと手軽にサクッと読めるように「マンガ版」や「図解版」などの”簡略本”が多く出版されています。
ですが著者は、「難しくてもまず原典を読むべき」と主張します。
なぜなら、簡略本は手っ取り早く分かったような気になるものの、多くの「切り捨てられた部分」に触れることはできないから。
その「切り捨てられた部分」にこそ、読むべきことが書かれていることが多々あると言われてます。
- 「簡略本→原典」ではなく
- 「原典→簡略本」という順番で読むべき
大事なのは、難しい部分を自分なりに解釈することで「考える力」が養われることです。
3) 本の「内容」よりも「考え方」が大事
読んだ本の内容は覚えておくべきという意見もありますが、著者は「忘れてOK」と述べています。
なぜなら、新しい情報や知識よりも、自分が何を思ってどう考えたかということが重要だから。
簡略本に飛びつくのは、「手っ取り早く情報を得よう」という意識が強すぎるのかもしれません。
例えるなら、テスト前に歴史の年号を丸暗記するようなもの。
そうした”知識”は時間とともに忘れられるのがオチです。
一方、知識と違い「考え方」は一度身につくと忘れることはありません。
たとえ本の内容は忘れても、考える力はあらゆる場面で応用できるのです。

要約③:頭を鍛える「時間」の習慣
1) すきま時間は「どう活用するか」を考える
どんなに忙しい人も「すきま時間」というのは少なからずあるはず。
時間を無駄にしたくない思いが強いとすきま時間を減らそうと考えがちですが、それはかえってストレスを増やす原因になりえます。
自分の行動だけならまだしも、他者のゆっくりな行動にイライラしていたら、、人間関係にも悪影響ですよね。
- すきま時間は「減らす」のではなく
- 「必ず発生するもの」と認識しつつ
- 「どう活用するか」を考える
その方がよっぽど生産的だと著者は主張します。
すきま時間の活用は、「短時間でできること」と「ある程度時間を使うこと」の2つを用意しておくことをオススメしています。
短時間ならスマホアプリなどでちょっとした勉強がよさそうです。

2) スマホとは「適度な距離感」を保つ
スマホは便利すぎる反面、接し方次第では時間をどんどん奪われる危険性があります。
ビルゲイツやスティーブ・ジョブズが自分の子供にスマホを与えなかったのは有名な話ですね。
とはいえ、意志の力だけでスマホと距離を取れたら苦労しませんね。
まずは、「スマホを近くに置かない状況」をつくることが重要です。
- ベッドにスマホを持ち込まない
- 充電器を自分がよく過ごす場所から遠ざける
といったことなら、すぐにでもできそうですね。
また、TwitterやYouTubeなどは時間泥棒の筆頭です。
それらは、あえてアプリを削除し、使いたい時はブラウザを利用しましょう。
検索してサイトを開くという”ひと手間”を加えることで、使うハードルを少し上げるのがポイントです。
3) 最適な「睡眠時間」を確保する
一般的に、睡眠時間は7〜8時間がベストと言われてますが、日本人の多くは7時間を切っています。
仮に6時間睡眠で1週間過ごすと、「睡眠負債」によって1日徹夜したくらいのダメージが脳にかかるそうです。
逆に、十分な睡眠を取れている人は仕事の能率が上がることも研究で明らかになっています。
みんなもっと「睡眠」の優先順位を上げるべき、というのが著者の考えです。
とはいえ、どうしても6時間しか寝れないような日もあるはず。
そういうときは、翌日の日中に昼寝する時間を確保して、少しでも「睡眠負債」を返すようにしましょう。
『頭を鍛える5つの習慣』とあわせて読みたいオススメ本3選

①『BRAINDRIVEN(ブレインドリブン)』(青砥瑞人)
脳を学び、神経科学を応用する時代を迎えました。
- 脳の中で起こっていることを解き明かし(WHAT)
- なぜそうなるのかを理解すれば(WHY)
- 高パフォーマンスな自分を創り出せる(HOW)

ビジネスパーソンの多くが課題に感じている「モチベーション」「ストレス」「クリエイティビティ」という3つのテーマについて神経科学の視点で解き明かしていきます。
-
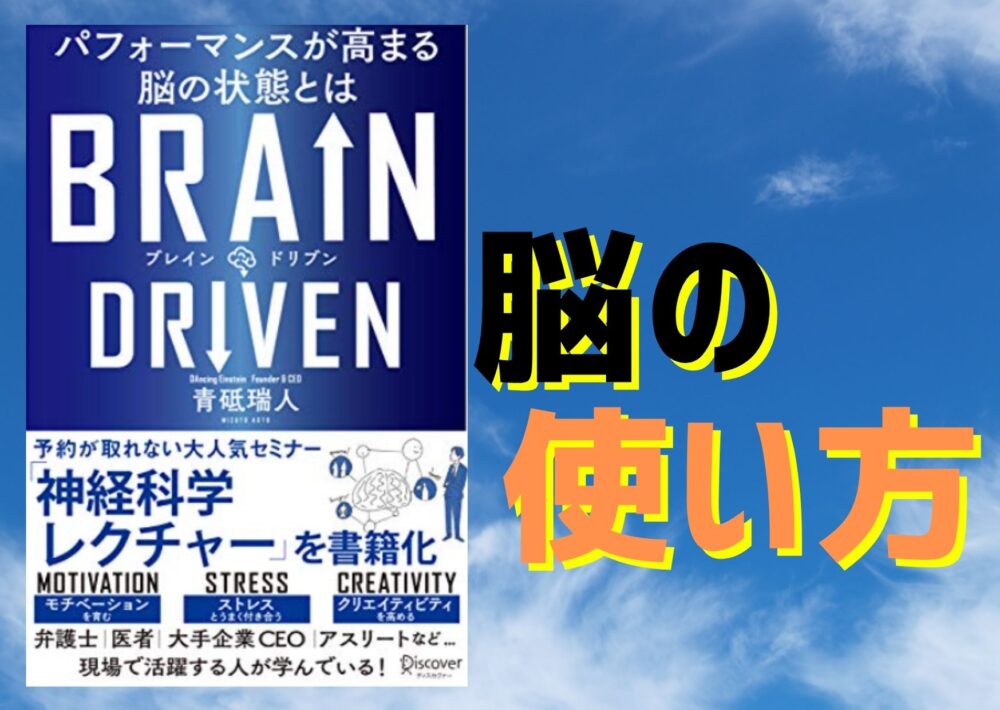
-
『BRAINDRIVEN(ブレインドリブン)』の要約【脳を学ぶ】
② 『やり抜く人の9つの習慣』(ハイディ・グラント・ハルバーソン)
目標に向かってやり抜ける人は、才能があるからではなく、ある種の思考や行動によって自らを成功に導いている。
そう著者は主張します。
その思考や行動は「当たり前」に思えるものかもしれませんが、
- 「当たり前でカンタンに実行できること」と
- 「誰もが当たり前に実行していること」は
決してイコールではありません。
-
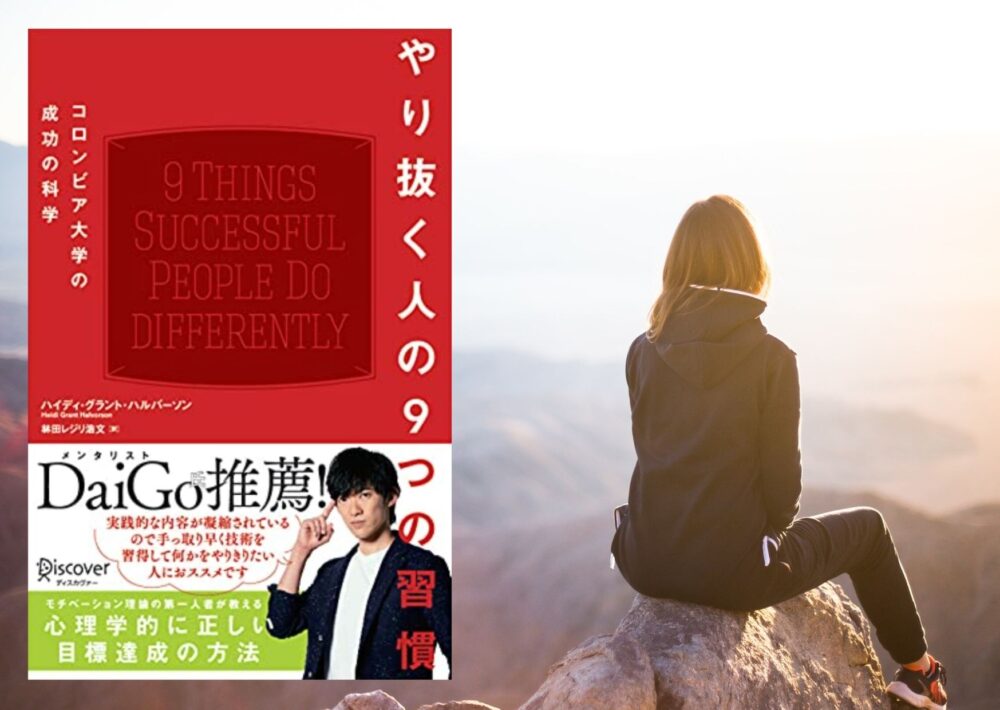
-
『やり抜く人の9つの習慣』の要約・感想【コンパクトなお宝本】
③『成長マインドセット』(吉田行宏)
- なかなか営業成績が上がらない
- 部下の数字が伸びない
- 上からのプレッシャーもある
そんな悩みを抱える主人公が、ふらっと入ったカフェのマスターから”成長するためのマインドセット”を教わるお話です。
成長を阻害するもの、促進するものをストーリー形式でわかりやすく学べる1冊。
-
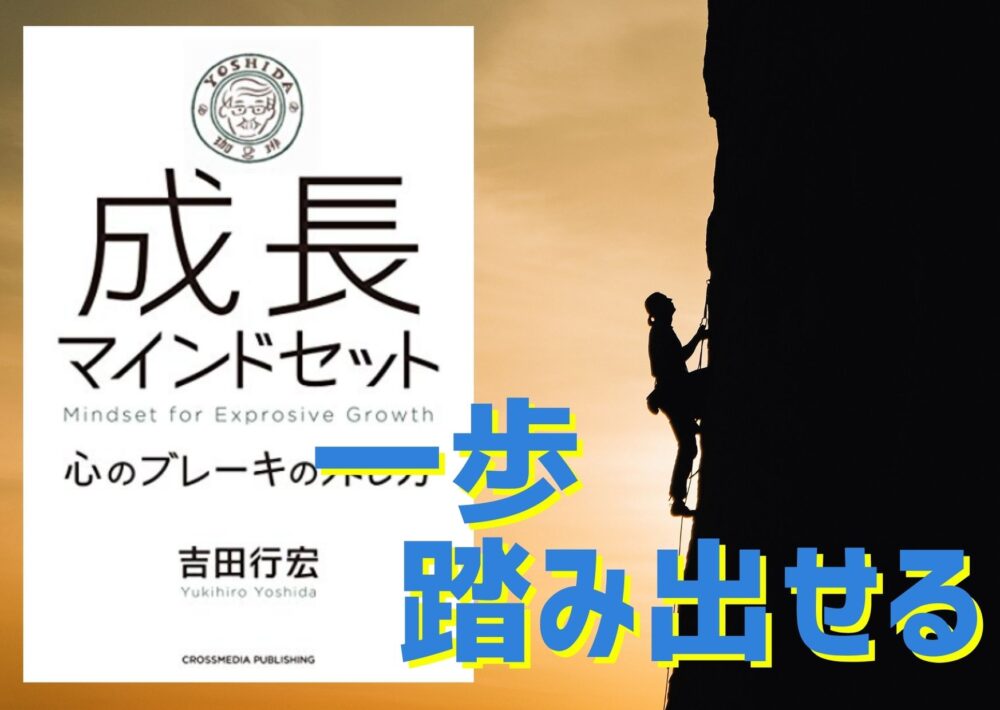
-
『成長マインドセット』の要約【アイスバーグで心のブレーキを外そう】
まとめ:天才とは、努力する凡才のことである

まとめます。
頭を鍛える「勉強」の習慣
- 「小さな目標」をクリアしていく
- 自分に合った勉強法を確立する
- 勉強を始めるタイミングは「今」が一番
頭を鍛える「読書」の習慣
- 「冷めた読み方」で思考力を磨く
- 「原典」にチャレンジする
- 本の「内容」よりも「考え方」が大事
頭を鍛える「時間」の習慣
- すきま時間は「どう活用するか」を考える
- スマホとは「適度な距離感」を保つ
- 最適な「睡眠時間」を確保する
アインシュタインは「天才とは、努力する凡才のことである」という言葉を残しています。
天才と凡才を「先天的な才能」として片付ければ努力しなくて済む分ラクかもしれませんが、本当の天才は日々の習慣の積み重ねから生まれるようです。
天才に近づく方法を知りたい方は、いちど本書を手にとってみることをオススメします。
電子書籍のサブスクKindle Unlimitedの無料体験でも読めるので、フルで読みたい方はどうぞ。
今回は以上です。