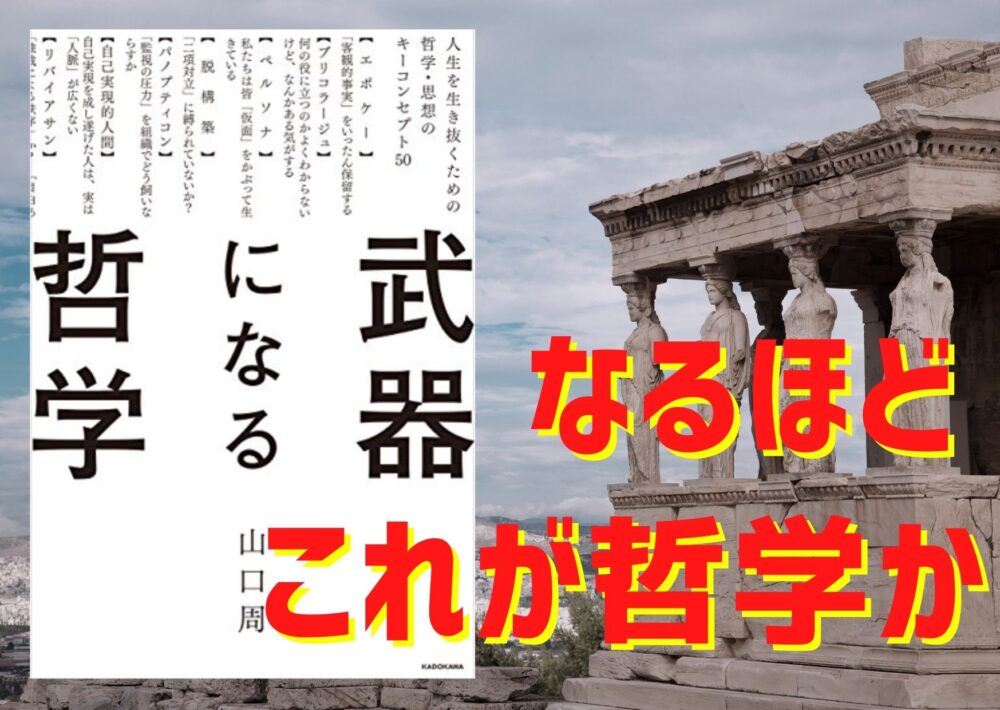この記事で分かること
- 「哲学」が武器になる理由が分かる
- 「人」に関するキーコンセプトが分かる
- 「思考」に関するキーコンセプトが分かる
本書をフルで読みたい方は、下記2サービスがコスパ最強でオススメですよ!
- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited
の無料体験で読む
- AmazonオーディオブックAudible
の無料体験で聴く
それではいってみましょう。
もくじ
『武器になる哲学』の基本情報【役に立たない学問No.1?】
まずは『武器になる哲学』の基本情報について見ていきます。
書名 :武器になる哲学
著者 :山口 周
出版月:2018/5/18
出版社:KADOKAWA
定価 :¥1,760 (税込)
著者である山口周さんのプロフィールはコチラです。
1970年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て、組織開発・人材育成を専門とするコーン・フェリー・ヘイグループに参画。同社のシニア・クライアント・パートナー。専門はイノベーション、組織開発、人材/リーダーシップ育成。株式会社モバイルファクトリー社外取締役。
-Amazon著者情報より抜粋-
哲学が役に立たない学問の代表と言われる原因は、そのアプローチ方法にありました、
実際は、ビジネスマンがクリティカルシンキングを持つうえで大きな助けとなる知識が満載なのです。

『武器になる哲学』の要約【人生を生き抜く教養】

それでは、『武器になる哲学』の内容を3つのパートに分けて要約していきます。
- なぜ「哲学」が武器になるのか
- 「人」に関する武器になる哲学
- 「思考」に関する武器になる哲学
順番に見ていきましょう。
要約①:なぜ「哲学」が武器になるのか
まずは、哲学がなぜ武器になるのか、そのメリットを見ていきます。
哲学を学ぶメリット
- 状況を正確に洞察する
- 批判的思考のツボを学ぶ
- アジェンダ(課題)を定める
- 二度と悲劇を起こさないために
ひとつずつ解説しますね。
1) 状況を正確に洞察する
- 問題の輪郭がどうにも定まらない
- 問題の原因が整理できない
そんなとき、過去に哲学者が提案した様々な思考の枠組みやコンセプトを目の前の状況に当てはめて考えることで、状況をより正確に洞察できます。
例えば、いま世界で起きている「教育革命」は、弁証法(後述してます)という哲学コンセプトを知ってると、

という洞察につながります。
このように、状況を洞察する際の強力なツールになるのが哲学なのです。
2) 批判的思考のツボを学ぶ
過去の哲学者が向き合ってきた問いは、
- 「What」の問い(世界はどう成り立っているのか)
- 「How」の問い(その中でどう生きるべきなのか)
この2種類しかありませんが、未だに決定打と言える回答は示されていません。
なぜなら、哲学の歴史は「提案→批判→再提案」の連続で出来上がっているから。
この考えは現代のビジネスシーンでも求められますよね。
- かつてはうまくいっていた仕組みを
- 時代の変化に適応する形で変更していく
重要なのは、「変化には必ず批判が伴う」という点です。
難しいのは、「新たに始めること」ではなく「古いものを終わらせること」ではありませんか?

3) アジェンダ(課題)を定める
3つ目のメリットは「課題を定める」ことです。
なぜなら、全てのイノベーションは「課題の解決」によって実現されているから。

- 課題設定に必要なのが「常識の疑う」ことであり
- 常識を疑うために必要なのが「教養」であり
- 教養を映し出すレンズが「哲学」である
自分の知識と目の前の現実を比べて、「いま、ここだけで通用している常識」を浮き上がらせるために、哲学が一役買ってくれるのです。
4) 二度と悲劇を起こさないために
人類の過去の歴史は、邪悪な悲劇によって真っ赤に血塗られており、そのような悲劇は「ごく普通の人々」の愚かさによって招かれています。
哲学者たちは、数々の悲劇を前にして、
- なぜ人はこれほど邪悪になれるのか
- 我々は愚かさをどう克服すべきなのか
ということに徹底的に向き合ってきました。

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という格言を聞いたことあると思います。
- 過去の悲劇を繰り返すのか
- より高い知性を発揮するのか
その差は、「失敗の教訓をどれだけ学べるか」にかかってると著者は主張します。
要約②:「人」に関する武器になる哲学
1) 論理だけでは人は動かない
論理思考が優れた人ほど、論理で説得すれば人は動くと誤解しがちですが、
- 説得より「納得」の方が
- 納得より「共感」の方が
が人は動くものです。
古代ギリシアの哲学者アリストテレスは、人の行動を本当の意味で変えさせるには、「ロゴス」「エトス」「パトス」の3つが必要であると説いています。
- ロゴス・・・ロジック。論理がムチャクチャだと賛同が得られない。
- エトス・・・倫理。道徳的に正しくないと納得できない。
- パトス・・・パッション・情熱。思い入れを感じないと共感できない。

2) 悪事は、思考停止した凡人によってなされる
悪事というものは、それを意図する何者かによって「能動的」になされるものと考えられがちです。
そんな中、アメリカの哲学者アーレントはこう説いています。
「悪事を意図することなく「受動的」になされることにこそ、悪の本質があるかもしれない」

具体例で補足します。
ナチスドイツにおいて、ユダヤ人600万人を虐殺したアイヒマンという男が捕らえられたとき、彼の風貌が「ごく普通の気弱そうな人物」であることに関係者は大きなショックを受けたそうです。
アイヒマンは殺意に満ち溢れていたわけではなく、ただ純粋に与えられた任務を懸命にこなしてただけなのでした。
つまり、アーレントが言いたいのは「悪とは、システムを無批判に受け入れること」ということ。
現代でも、大規模な組織犯罪や不祥事は後を経ちませんよね。
自分で考えることを放棄してしまった人間は、誰でもアイヒマンのようになる可能性があるわけです。
3) 認知的不協和
人は、自分の認知と矛盾する行動をした場合、この不協和を解消するために自分の認知を改めようとする性質があります。

また具体例で補足します。
朝鮮戦争の時代、中国共産党の捕虜となった米兵の多くが共産主義に洗脳される事態が起こりました。
そのときやってたのが「お菓子などの”小さな褒美”を与えて、共産主義を擁護するメモを書かせる」という手法。
- 「共産主義は敵である」という自分の認知と
- 「共産主義を擁護するメモを書いた」という行動
ここに「不協和」という矛盾が発生しています。
こうなると人は自分の行動を合理化するために、自分の認知を「共産主義」に変えてしまうのです。
このとき、”小さな”褒美であることも重要なポイント。
褒美が大きいと”褒美のために嫌々やった”となるので不協和は小さくなってしまいます。

要約③:「思考」に関する武器になる哲学
1) 弁証法
弁証法とは、「対立する考えをぶつけ合わせ、アイデアを発展させる」という”真理に至るための方法論”のひとつです。
弁証法
- 命題(テーゼ)Aが提示される
- Aと矛盾する反命題(アンチテーゼ)Bが提示される
- AとBの矛盾を解決する統合された命題(ジンテーゼ)Cが提示される
例えば、「これは長方形だ」というテーゼAに対し、「いや、円だ」というアンチテーゼBを主張するとします。
2D空間で考えると双方が両立することはありませんが、3Dで考えると「それって円柱じゃね?」というジンテーゼCに発展するわけです。
この傾向は、歴史にも当てはめることができます。
「教育」の歴史で考えると
- テーゼ:村の子供を集め、多様な教育を行う「寺子屋」
- アンチテーゼ:同い年の子供を集め、画一的な教育を行う「学校」
- ジンテーゼ:ICTの活用で、同い年の子供を集めつつ、多様な教育を行う
歴史を紐解くと見えてくるのが、弁証法は「発展」と「復古」が同時に起こるということ。
ICTの活用で、学校が「発展」したカタチとも言えますが、ある部分では、寺子屋に「復古」したとも言えますよね。
一見、新しいように見えるものも、長い時間軸で考えると「古いものが何らかの発展的要素を含んで回帰してくる」ということなのです。
これから起こる変化も、もしかしたら古いものがより便利になって回帰してくるかもしれません。

2) 言葉の豊かさは思考の豊かさに直結する
- 「モノ」という実体があって
- それに対して「コトバ」が後追いで付けられた
私たちはそう考えがちですが、果たして本当にそうでしょうか?
例えば「蝶」と「蛾」。
2種類の虫がもともと存在したうえで名付けられたように思えますが、フランス語では「蝶」と「蛾」を区別せず「パピヨン」という言葉に包括されています。

また、「恋」も「愛」も英語では「LOVE」なので、アメリカ人に「恋と愛の違いとは?」みたいな疑問は生まれません。
ポイントは、私たちは”自分の持っている言語の枠組み”でしか世界を把握することができないということ。
言葉(概念)の豊かさは、目の前の事象をより正確に洞察することにつながるわけです。
3) 世の中は、いきなり「ガラリ」とは変わらない
定説がくつがえり、ものの見方や考え方がガラッと変わることを「パラダイムシフト」と言ったりします。
例えば、かつては誰もが納得していた「天動説」も、コペルニクスが説いた「地動説」によって大きなパラダイムシフトが起きました。
歴史上の革命や発見を「後追い」で学んでいる我々は、世の中がいきなりガラッと変わったと思いがちですが、地動説が受け入れられるまでには、コペルニクスが亡くなってから100年以上かかってます。
- パラダイムシフトはある日を境に急に変わるわけではなく
- 100年単位の時間をかけて徐々にシフトするということ
逆に言えば、我々が生きている「いま」も、長い歴史で見れば何らかのパラダイムシフトの最中なのかもしれません。
『武器になる哲学』の感想
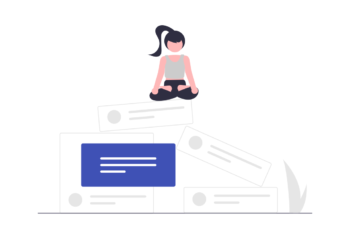
- 哲学の入門書として最適
- ビジネスマンの思考の幅を広げる
そんな1冊です。
なぜなら、多くの哲学入門書は時間軸をベースにしており、序盤の古代ギリシア哲学があまりにもつまらないから。
現代人にとっては「まぁ、そりゃそうでしょ・・」となることが多く、哲学を学ぶ「意味」を見出せなくなるわけです。
その点で本書は、「人」「組織」「社会」「思考」という使用用途別に構成されています。
また、哲学者が導き出した「アウトプット」だけでなく、そこに至る「プロセス」からの学びを重視してるのもポイント。
- 部下が思うように動いてくれない
- 仕事にやる気が出ない
- 業務改革をしたい
そんな悩みを持つビジネスマンは、哲学から多くのヒントを得られるんじゃないでしょうか。
個人的に刺さったのは「現在も何らかのパラダイムシフトの最中かもしれない」ということ。
そう考えると、”もしかして?”って思うのがたくさんありますよね。
- 現金からキャッシュレスへ
- 年功序列から成果主義へ
- 終身雇用から転職&副業時代へ
- ガソリンから電気自動車へ
- 所有から共有の時代へ

まとめ:間違いなく「一生使える教養」

まとめます。
哲学が武器になる理由
- 状況を正確に洞察する
- 批判的思考のツボを学ぶ
- アジェンダ(課題)を定める
- 二度と悲劇を起こさないために
「人」に関するキーコンセプト
- 人を動かすのに必要なのは「論理」と「倫理」と「情熱」
- 思考停止した人間は「悪」を「悪」であると気づけない
- 人は自分の行動によって認知が変わる生き物
「思考」に関するキーコンセプト
- 新しいものは「発展的要素を含んだ古いもの」かもしれない
- 人は”知ってる言語の枠組み”でしか世界を把握できない
- 現在も何らかのパラダイムシフトの最中かもしれない
この記事で紹介した哲学はほんの一部です。
本書では全部で50のキーコンセプトが紹介されています。
哲学慣れしてない自分が読破するにはちょっと気合い必要でしたが、これは間違いなく「一生使える教養」ですよ。
「よくそんなこと思いつきましたね!」なんて言われたい方は、いちど本書を手にとってみることをオススメします。
本書をフルで読みたい方は、下記2サービスがコスパ最強でオススメですよ!
- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited
の無料体験で読む
- AmazonオーディオブックAudible
の無料体験で聴く
-

-
【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?
今回は以上です。