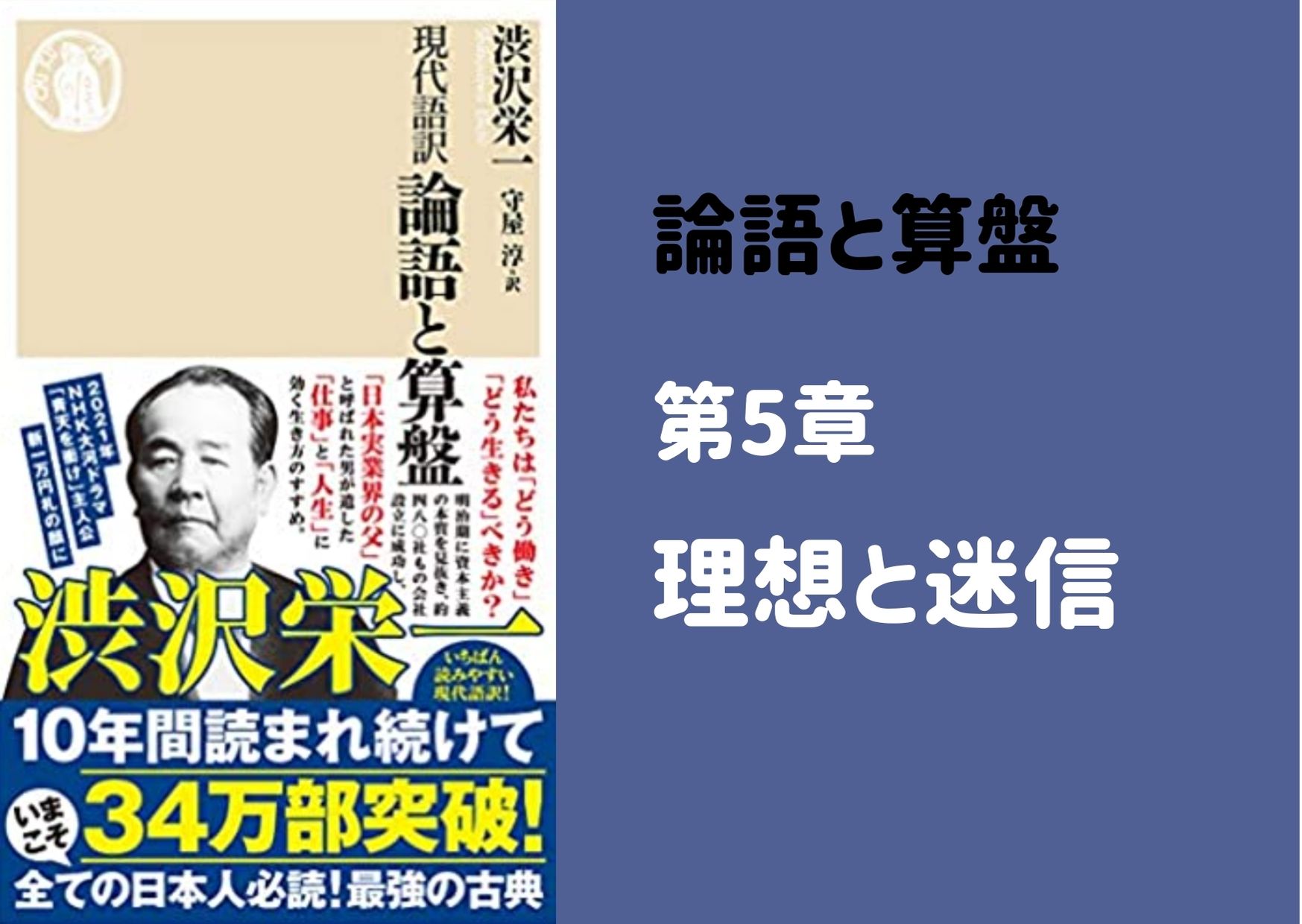日本実業界の父・渋沢栄一の著書『論語と算盤』の要約を、各章ごとにシリーズでお送りしております。

各章に順序性はないためどこから読んでも大丈夫ですが、前章をまだ読んでない方は上のリンクから各記事へジャンプできるのでよかったらどうぞ。
AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。
【論語と算盤】第5章「理想と迷信」の要約
第5章のメニューは以下の通りです。
- 熱い真心が必要だ
- 道徳は進化すべきか
- 1日を新たな気持ちで
- 修験者の失敗
- 本当の「文明」
では順番に見ていきましょう。
①熱い真心が必要だ
どんな仕事でも、自分がワクワクするような面白み(趣味)を持つべきです。
命令に従って役割をこなすだけならただのマニュアル人間になってしまいます。
趣味を持って取り組むと
- この仕事はこうしたい、ああしたい。
- こうなったら、これをこうすればこうなる。
というように、必ずその仕事には心がこもるに違いありません。
自分の務めに対しては、この熱い真心がなくてはなりません。
孔子の言葉にも
「理解することは、愛好することの深さに及ばない。愛好することは、楽しむ境地の深さに及ばない。」
とあります。
またそれは引退後も同じで、ただ食べて寝てその日を送るだけの老後は「肉の塊」だと表現しています。
②道徳は進化すべきか
「古いものは自然に進化すべきだ」
そうダーウィンも言っているように、”物事の善悪に関する道徳”は世の中の進歩とともに変わっていくべきです。
例えば、大昔は親孝行のためには我が子も犠牲にするような考えも善とされていましたが今ではありえません。
しかし一方で、仁や義といった”社会正義のための道徳”は今も昔も同じです。
学問やモノがいかに発達しても、人としての根幹部分は変わらないものなのです。
③1日を新たな気持ちで
社会や学問は日々進歩していますが、人間はそうでもありません。
年月を重ねるごとにマイナス面が出てきたり、長所が短所になったりしています。
特に問題なのは、悪い習慣づけが続くことです。
すべてが形式的になると精神が先細りしてしまうので「1日を新たな気持ちで」という心掛けが肝心です。
悪い慣習が長いこと染みついた古い国は、形式に流される風潮が出やすいもの。
徳川幕府が倒れたのもこの理由と言えます。
そのためには民衆を導くようなまともな宗教も必要ですが、世間では迷信などもいまだに盛んです。
「信念が強ければ道徳は必要ない」と西洋人は言いますが、日本人もそのくらいの信念を持たなければなりません。
④修験者の失敗
迷信嫌いの渋沢栄一にはこんなエピソードがあります。
渋沢には脳の病を患った姉がいましたが、迷信家の親戚が「この病気はこの家の祟りかもしれない」と言って修験者が祈禱しに来ました。
「50年以上前からこの家にいる無縁仏が祟りを起こしている。祠(ほこら)を作って祀ってあげればよい。」
と勧める修験者に対して、渋沢は尋ねます。
「50年以上前とは年号にするといつ頃ですか?」
「天保3年の頃だ。」
と答えますが、天保3年はまだ20年ほど前です。
「無縁仏がいることまで見通せる神様が年号を間違えるなどあり得ない!」
と言ってその修験者を返り討ちにしたそうです。
それが村に伝わり、修験者を村に入れないようになったそうです。

⑤本当の「文明」
文明国というのは、
- 国の体制が明確で
- 制度がきちんと定まっていて
- 必要な設備が整っていて
- 法律も完備し
- 教育制度も行き届いている
そんな「枠組み」が備わっています。
とはいえ枠組みだけでは不十分で、一国を維持し発展させる実力も備える必要があります。
枠組みばかり整備してもそれを使う人の知識や能力が伴ってなければ本当の文明国とは言えないワケです。

この時の日本はどうかと言えば、枠組みの面に関しては申し分ありませんが、実業の育成が進んでいないため経済的豊かさが不足しているそうです。
とは言っても国の文明を発展させるためには軍事力にお金を使う必要もあります。
つまりは、内政と外交のバランスを崩さないように進めることが重要です。文明国とは力強さと経済的豊かさを兼ね備えているものです。
【論語と算盤】第5章「理想と迷信」まとめ
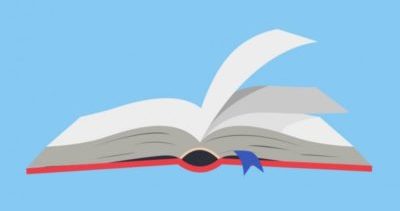
最後に、第5章「理想と迷信」の要点をざっくり振り返ります。
- どんな仕事でも面白み(趣味)を持つべし
- 仁や義といった”社会正義のための道徳”は今も昔も同じ
- 悪い習慣が染みつかないよう強い信念が必要
- 迷信に惑わされてちゃダメ
- 文明国とは力強さと経済的豊かさを兼ね備えているもの
第6章はコチラからどうぞ!

-
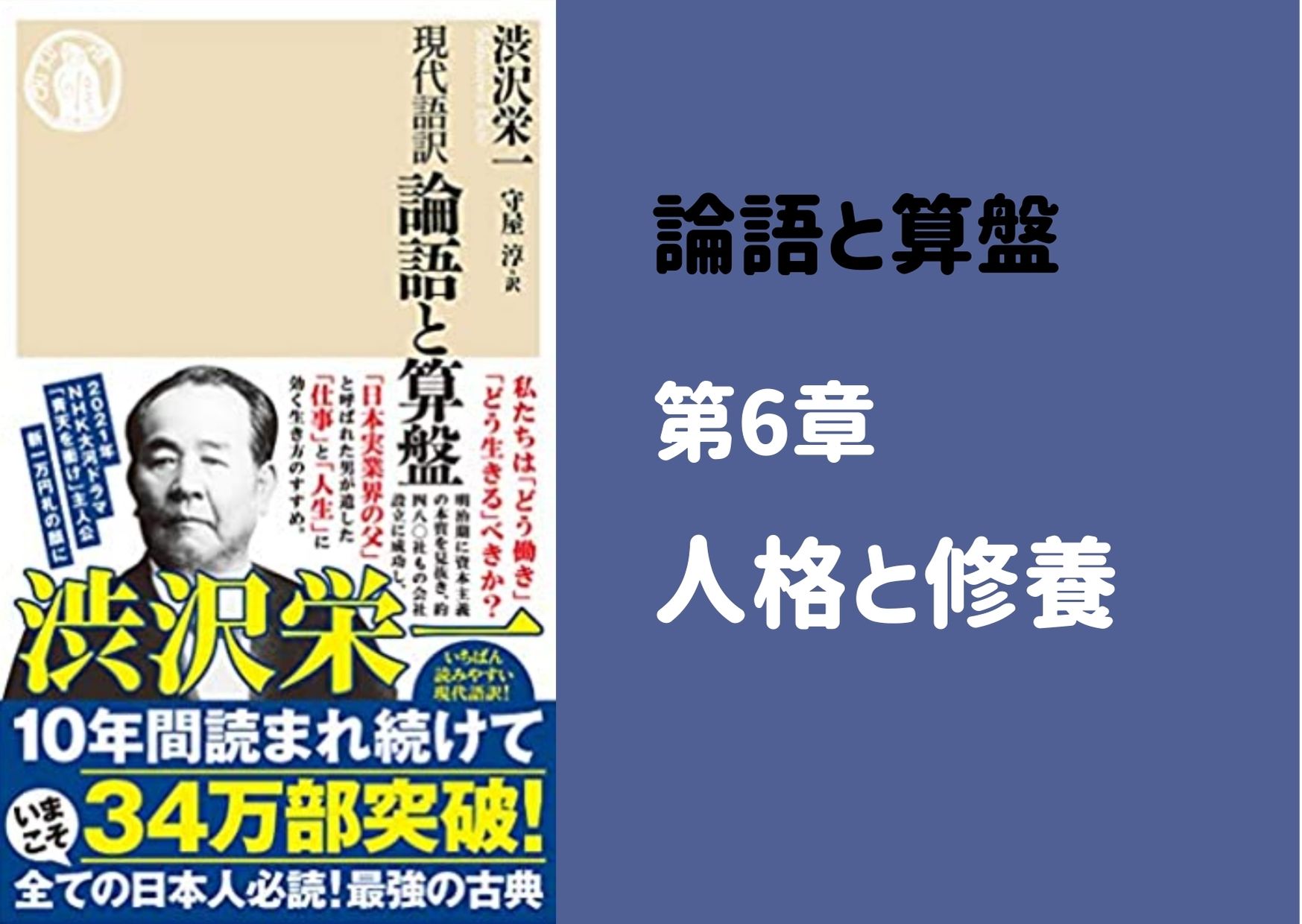
-
渋沢栄一『現代語訳:論語と算盤』第6章「人格と修養」の要約まとめ
続きを見る
渋沢イズムをより深く知りたい方は本書をいちど手に取ってみることをオススメします。
マンガ版も要点が分かりやすくてオススメですよ。
AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。
-

-
【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?
続きを見る
今回は以上です。