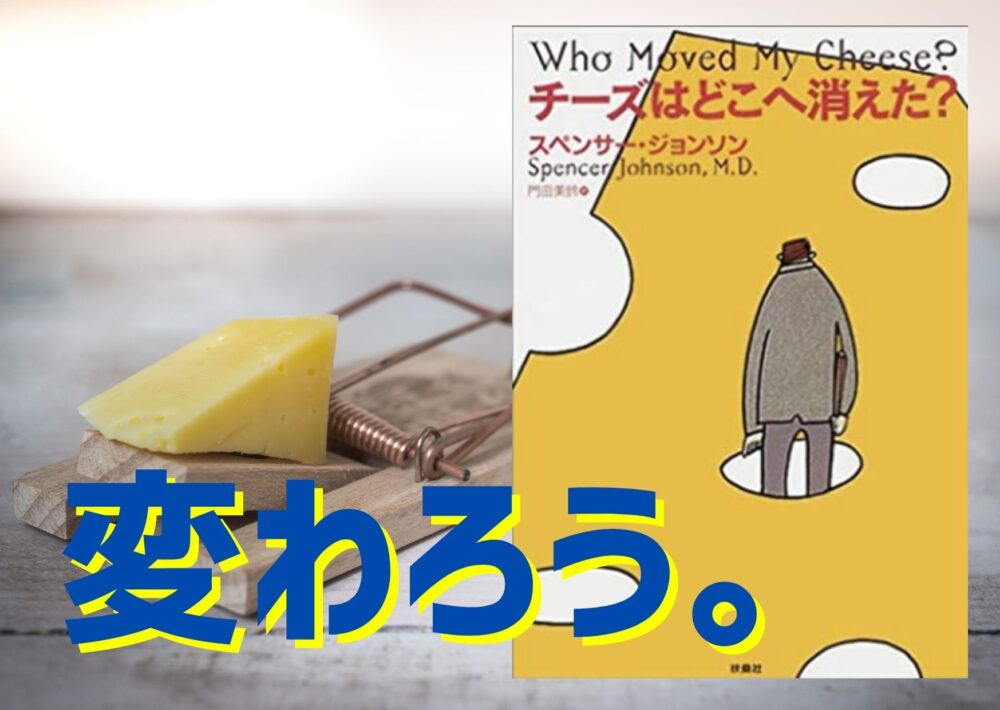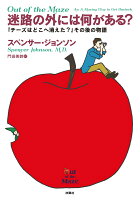この記事で分かること
- 『チーズはどこへ消えた?』の要約・感想が分かる
- 変化に対応する行動パターンが分かる
- 変化を阻害する心の要因が分かる

もくじ
『チーズはどこへ消えた?』の基本情報【世界的ベストセラー】
まずは『チーズはどこへ消えた?』の基本情報について見ていきます。
書名 :チーズはどこへ消えた?
著者 :スペンサー ジョンソン
出版月:2000/11/27
出版社:扶桑社
定価 :¥922(税込)
著者であるスペンサー ジョンソンさんのプロフィールはコチラです。
多くの企業やシンクタンクに参加し、ハーバード・ビジネス・スクールの名誉会員に列せられている、アメリカ・ビジネス界のカリスマ的存在。経営学の古典的名著でありロングセラーの『1分間マネジャー』(共著、ダイヤモンド社刊)をはじめ、『1分間意思決定』(ダイヤモンド社刊)、『プレゼント』(扶桑社刊)など多数の著書を発表している。心理学者であり、心臓のペースメーカーの開発にたずさわった医学博士でもある。著書のなかでも、寓話に託して、変化にいかに対応するべきかを語った『チーズはどこへ消えた?』(扶桑社刊)は、日本でも400万部を超える爆発的なヒットとなった。『チーズはどこへ消えた?』はアメリカでの刊行(1998年)当初から、IBM、アップル・コンピュータ、GM、メルセデス・ベンツなど、世界を代表する企業や官公庁で研修のテキストに採用された。日本でも、ビジネスマンのみならず、働く女性たちや主婦層、小学生から高齢者まで、広範な読者に受け入れられ、大きな反響を呼んだ。その後、『頂きはどこにある?』(2009年/扶桑社刊)を刊行。2017年、78歳で逝去。本書『迷路の外には何がある?』が遺作となる。
-扶桑社 著者プロフィールより抜粋-
本書の登場人物は、2人の小人と2匹のネズミ。
- 小人コンビ ・・ヘム&ホー
- ネズミコンビ・・スニッフ&スカリー
この2人と2匹が、ある「迷路」の中で「チーズ」を追い求める物語です。
なんだそれ?と言われそうですが、
- チーズ→人生で求めるもの(お金・地位・自由など)
- 迷路 →チーズを追い求める場所(会社や家庭など)
を象徴しています。
迷路の中で起こる「変化」に対して
- 4者がどう行動するのか
- 自分だったらどうするか
といったことを考えながら読むと楽しめるんじゃないかと思います。
『チーズはどこへ消えた?』の要約【時代は変化する】

それでは、『チーズはどこへ消えた?』のポイントを3つのパートに分けて要約していきます。
- 物語のあらすじ
- ネズミコンビの行動ポイント
- 小人コンビの行動ポイント
順番に見ていきましょう。
要約①:物語のあらすじ
まずは本書の大まかなあらすじをサラッと見ていきましょう。
1) 大量のチーズを発見
彼らはいつも迷路の中でチーズを探しまわっていました。
ある日、チーズステーションCで大量のチーズを発見します。
それからは、ネズミも小人も毎日チーズステーションCへ向かいチーズを堪能しますが、それぞれの行動に少しずつ違いがあらわれます。
- ネズミコンビ
→毎日早起きしてチーズステーションCに変化がないか確認していた - 小人コンビ
→「チーズがあるのが当然」と考えて朝の行動もゆっくりになった
2) チーズが消えた?
ある朝、チーズステーションCに行ってみるとチーズがなくなっていました。
ネズミコンビはすぐに新しいチーズを求めて迷路へ出発しましたが、小人コンビは「なぜ消えた!?」と立ち尽くします。
そして「いつかチーズは戻ってくる」と考え、その場に待機するのでした。
そうこうしてるうちに、ネズミコンビはチーズステーションNでより大量のチーズを発見します。
3) 新たなチーズを求めて
待てど暮らせど小人たちのもとにチーズが戻ってくることはなく、次第にホーとヘムの意見が分かれます。
- ホー・・チーズは戻ってこない。新たなチーズを探しに行くべき。
- ヘム・・新しいチーズなんてないかもしれない。ここで待機すべき。
結局、ホーは1人で迷路へ出発します。
ホーは迷路で迷いながらもこれまでを振り返りつつ、”変化に対する立ち回り方”を学んでいきます。
そして、ネズミコンビと同じチーズステーションNになんとかホーも辿り着くのでした。
要約②:ネズミコンビの行動ポイント
では、変化に対応し新しいチーズに辿り着いたネズミコンビの行動ポイントを見ていきます。
1) 変化を探知し備えていた
ネズミコンビは好みのチーズを発見したあとも、チーズステーションCの状態に変化がないか毎日確認していました。
だんだんチーズが少なくなってることに気づいてたため、「いづれなくなる」と覚悟できてたわけです。
- 小さな変化に気づくことで
- やがて起こる大きな変化にも備えられる

2) 物事をシンプルに捉えつつ素早く行動
チーズが消えた後も、わざわざ事態を分析するようなことはしません。

すぐに新しいチーズを探しに出発します。
すぐ動けるよう常にランニングシューズを首から下げてたのもポイントです。
- 状況が変わったから
- 自分の行動も変わる
考え方はいたってシンプル。
要約③:小人コンビの行動ポイント
続いて、変化に乗り遅れた小人コンビ(特にヘム)の行動ポイントです。
1) 現状に対する「慢心」
最初はスニッフとスカリーと同じように、早起きしてチーズステーションCへ行ってましたが、次第に遅く起きてゆっくり行くようになります。
- チーズはそこにあるのが当たり前
- これだけあればずっと安泰
と安心しきっており、少しずつチーズが減っていることに全く気づきません。
なんなら、「チーズは自分たちのもの」くらいに考えていました。
2) 変わることへの「恐怖」
ネズミコンビはすぐに次のチーズを探しに出ましたが、ヘムとホーは途方に暮れるだけでした。
そして、「いづれチーズは戻ってくるはず」という根拠のない理由で「待機」という選択をします。
この選択の奥にあったのは「恐怖」です。
- 新しいチーズへの「希望」よりも、チーズが見つからない「恐怖」
- 慣れた場所への「安心」よりも、見知らぬ土地への「恐怖」
物事を複雑に考えるあまり、「恐怖」が勝ってしまい行動できなくなります。
3) 異常事態に対する「他責」の考え
チーズが消えた後も、かたくなに変わろうとしないヘムは理由をこう主張します。
この事態は我々のせいじゃないからだ。誰か他のもののせいなんだから、我々はこうなったことで何かもらうべきだ。
この根底にあるのは、「チーズは自分たちのもの」という考え。
自分のチーズが消えたのだから補償してもらうのは当然と思っています。
人が変化を前にしたときに最大の障害となるのは「自分自身」です。

『チーズはどこへ消えた?』の感想【人間は現状維持が好き】

1時間ほどでサクッと読めてしまうくらいのボリュームですが中身は非常に濃く、状況の変化に対する人間の思考や行動パターンが凝縮されていると思いました。
多くの人は、「ヘムは愚かだな」と思うはずですが、ヘムと同じような思考は誰しも脳に備わってるものです。

変化を阻害しがちなバイアス
- 現状維持バイアス
→未知なるモノを避けて現状を望む作用 - サンクコストバイアス
→「ここまでやったのに」と思ってやめられない - 損失回避バイアス
→「得」を取るよりも「損」を避けようとする作用
変化に踏み切れない時は、自分の中にこういったバイアスが作動してないか確認するだけでも結果は変わってくるかもしれませんね。
『チーズはどこへ消えた?』とあわせて読みたいオススメ本3選

①『迷路の外には何がある?』(スペンサー・ジョンソン)
『チーズはどこへ消えた?』の続編です。
チーズステーションCに残ったヘムはその後いったいどうなったんでしょう。

②『諦める力』(為末大)
「諦める」という言葉にはネガティブな印象を抱きがちですが、目的達成のために手段を諦めることは決してネガティブではないと為末さんは主張します。

チーズステーションCを”諦める”考え方とリンクするはずです。
kindleunlimitedの30日無料体験で読めるのもいいトコロ。
-
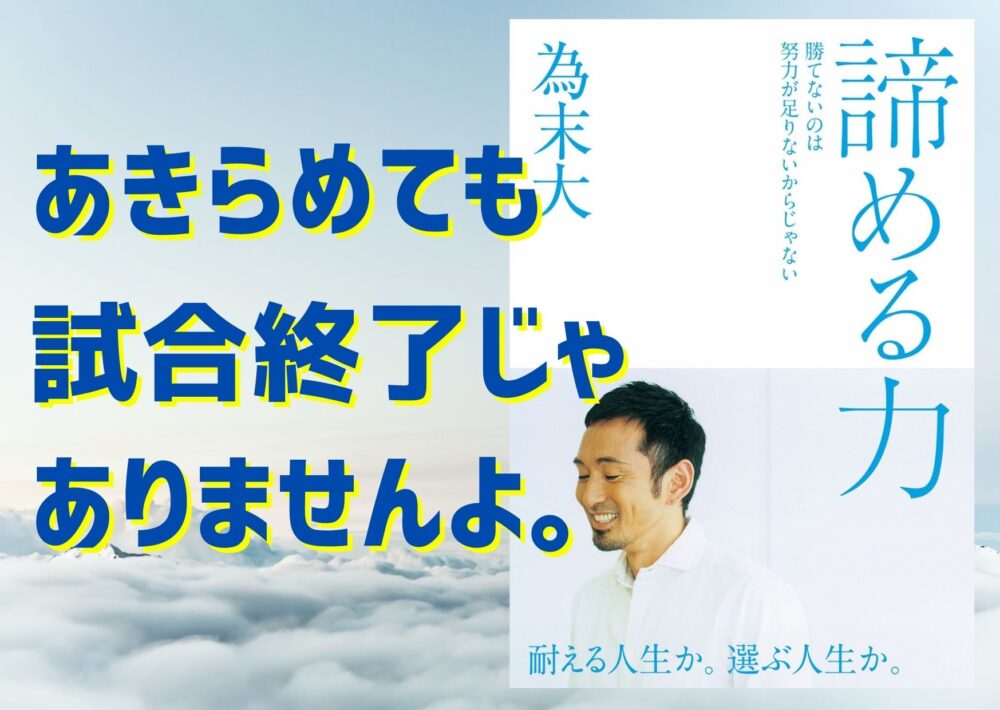
-
為末大『諦める力』の要約・感想まとめ【ダメなものはダメ】
③『「めんどくさい」がなくなる本』(鶴田豊和)
変わらなきゃ!と思っているときにジャマするのが「めんどくさい」という感情。
「めんどくさい」は喜怒哀楽・妬みに続く、人間が誰しも持っている”第6の感情”であり、めんどくさいがなくなると悩みの大半が解決するとのこと。

-
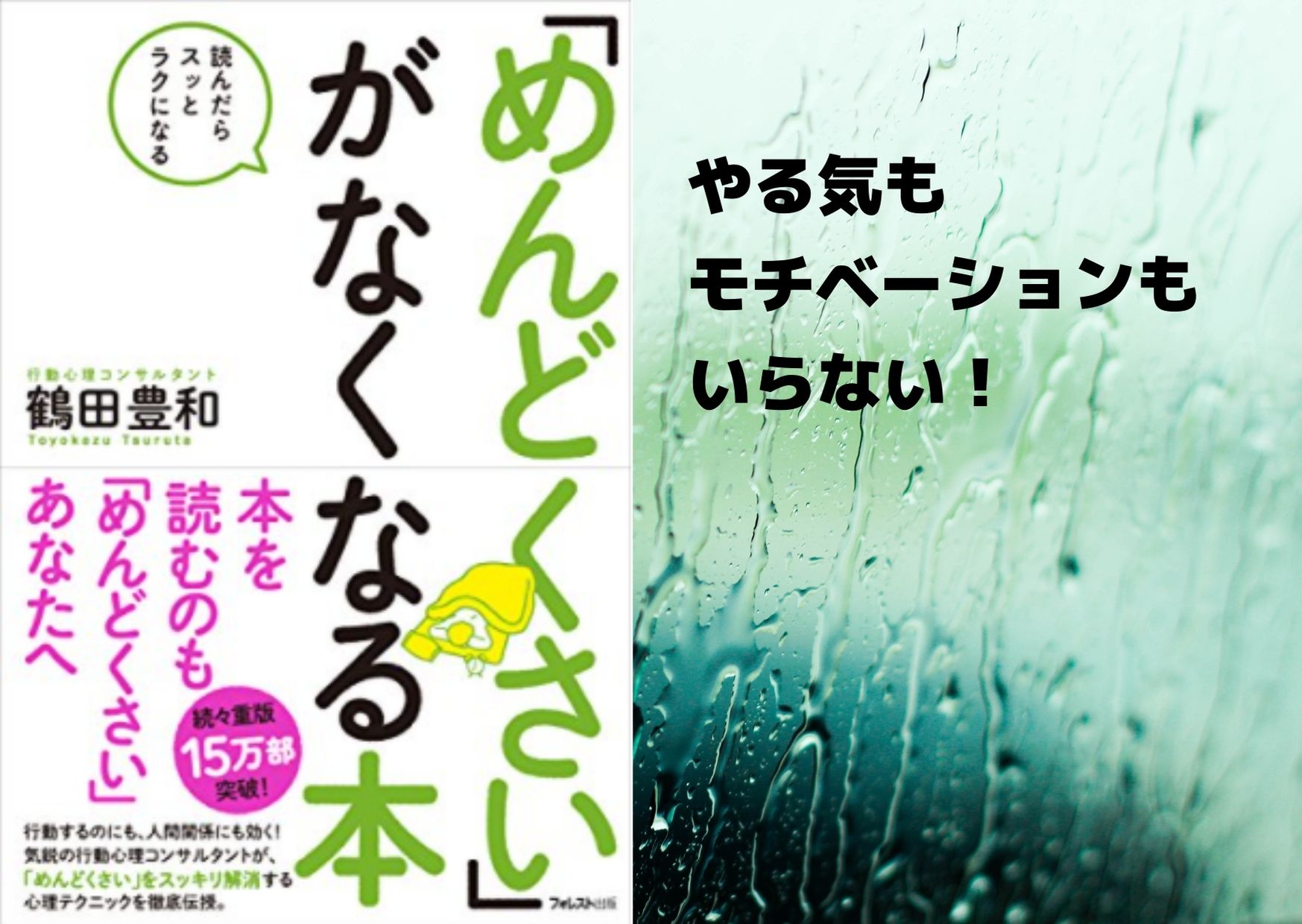
-
『「めんどくさい」がなくなる本』の要約・感想まとめ【自分に甘く】
まとめ:あなたのチーズはなくなりませんか?

まとめます。
- 変化は起きる前提で探知しつつ素早く適応しよう
- 変化を阻むのは「恐怖」と「バイアス」
- 自分が変わらなければ状況が変わることはない
- 狩猟から農耕に
- 刀から銃に
- 紙から電子に
- ガソリンからEVに
時代はつねに変化と共に流れるもの。

なくなるかも、と思った方は、いちど本書を手にとってみることをオススメします。
※マンガ版もあるのでよかったらどうぞ。
今回は以上です。