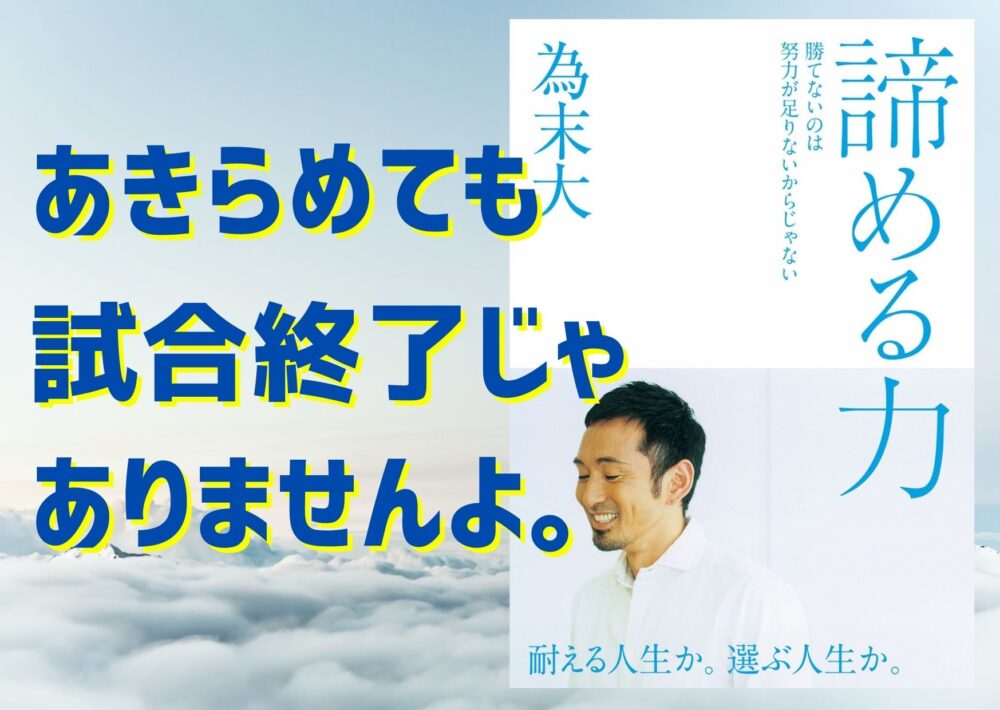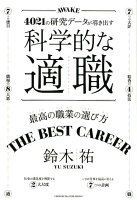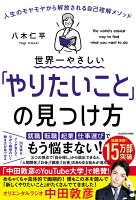この記事で分かること
- 『諦める力』の要約・感想が分かる
- 正しい「諦め方」が分かる
- 諦めさせない日本人の価値観が分かる
本書をフルで読みたい方は、下記2サービスがコスパ最強でオススメですよ!
- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited
の無料体験で読む
- AmazonオーディオブックAudible
の無料体験で聴く

もくじ
『諦める力』の基本情報【自分を悟る】
まずは『諦める力』の基本情報について見ていきます。
書名 :諦める力 勝てないのは努力が足りないからじゃない
著者 :為末大
出版月:2013/5/30
出版社:プレジデント社
定価 :単行本¥1,650、文庫¥770
著者である為末大さんのプロフィールはコチラです。
1978年広島県生まれ。2001年エドモントン世界選手権および2005年ヘルシンキ世界選手権において、男子400メートルハードルで銅メダルを勝ち取る。陸上トラック種目の世界大会で日本人として初のメダル獲得者。シドニー、アテネ、北京と3度のオリンピックに出場。男子400メートルハードルの日本記録保持者(2013年5月現在)。2003年、大阪ガスを退社し、プロに転向。2012年、日本陸上競技選手権大会を最後に25年間の現役生活から引退。現在は、一般社団法人アスリート・ソサエティ、為末大学などを通じ、スポーツと社会、教育に関する活動を幅広く行っている。著書に『走りながら考える』『走る哲学』『負けを生かす技術』などがある。
-Amazon著者紹介情報より抜粋-
「諦める」という言葉を聞いてポジティブなイメージを持つ方はほとんどいないと思いますが、そもそもの語源は「明らめる」からきているそうです。
”断念する”というよりも、”あきらかにする”という意味合いが強いわけです。
さらに、「諦」という漢字には「さとる」という意味もあります。
つまり、「諦める」という言葉は
- 自分の能力や状況を明らかにしつつ
- 今この瞬間にある自分の姿を悟る
という捉え方もできるわけです。
『諦める力』の要約【偏見に惑わされるな】

それでは、『諦める力』の内容を3つのパートに分けて要約していきます。
- 諦めるのは「手段」ではなく「目的」
- 日本人に植え付けられた価値観
- 世の中は平等じゃない
順番に見ていきましょう。
要約①:諦めるのは「目的」ではなく「手段」
1) 100mから400mハードルへ転向
為末さんは8歳の時に陸上を始め、花形種目の100mで頂点を目指します。
国内ではトップクラスの成績を残してきましたが、18歳の時に世界のレベルを目の当たりにして衝撃を受けたそうです。
- このまま100mで努力しても自分には先がない
- これだったら400mハードルでメダルを狙う方が現実的だ
そう考え、陸上の花形種目である100mを諦めて400mハードルに転向します。
とはいえ、周りからは「諦めるのはまだ早い」とも言われ、罪悪感や後ろめたさも感じながら競技を続けていました。
2) 勝つために「手段」を諦める
しかし、時間が経つにつれて、400mハードルを選んだことが腑に落ちるように気持ちが変化してきたそうです。
- 100mを諦めたのは勝ちたかったからだ
- だからこそ勝てないと思った100mは諦めた
- 勝つことを諦めたわけではない
つまり、「AがやりたいからBを諦めるという選択をしたに過ぎない」ということ。
多くの人は、「手段」を諦めることが諦めだと考えがちですが、「目的」さえ諦めなければ手段は変えてもいいというのが為末さんの考え方です。
- 「勝つ」という目的のために
- 「100m」という手段は諦め
- 「400mハードル」を選択した

3) 諦めることは「戦略」でもある
憧れの選手を目指して努力するのも立派ですが、憧れが成功を阻害する可能性もドライに認識すべきです。
人間には変えられないことの方が多いので、変わらなくても戦えるフィールドを探すのもひとつの戦略と言えます。
- ダメなものはダメ
- 無理なものは無理
と認めつつ、自分の強みをどう生かして勝つかを考える。

極端に言うと、
- 努力しなきゃ勝てないことよりも
- さしたる努力をしなくても勝てる
そんなフィールドが探す方が勝率は間違いなく上がります。
要約②:日本人に植え付けられた価値観
1) やればできる・・。
- やればできる
- 努力は裏切らない
- 諦めなければ夢はかなう
こういった言葉に励まされつつ成功した人がいるのも事実ですが、ひねくれた見方をするとこうも言えます。

論理的に突っ込んでいくと成功と努力の相関関係はどんどん曖昧になるものです。
アスリートの世界でも、ビジネスの世界でも「先が見えてくる年齢」があったりします。
そのときに「諦めなければ夢はかなう」というロジックだけでは、人生がつらくなってくるかもしれません。
2) せっかくここまでやったんだから・・。
経済学で「サンクコスト」という考え方があります。

日本人は「せっかくここまで頑張ったんだから」という考えに縛られがちです。
過去の蓄積を大事にするというと良く聞こえますが、実態は「過去を引きずってる」に過ぎません。
何かを諦める判断をするときは
- ”ここまでやったんだから”という「過去」と
- ”このさき成功しそう”という「未来」
どっちを見るかで、異なる結果をもたらすはずです。
3) 引退の美学
- 引退の美学
- 引き際の美学
といった言葉もあるように、大きな節目まで全力を尽くして引退するのが日本では美徳と考えられがち。
ドライに引退するアスリートに対しては本気でやってないという印象を持つかもしれませんが、実際はそのようなアスリートは星の数ほどいます。
その後に別の道で成功したとしてもメディアが取り上げることはまずありません。
海外の選手のように、引っ越しするくらいの感覚で軽やかに引退するのも全然アリではないでしょうか。
要約③:世の中は平等じゃない
1) 才能という階級
「諦める」ということを掘り下げていくと「階級」という問題に行き着きます。
生まれによる階級がなくても、才能による階級が存在するのです。
- 生まれながら早く走れる人もいれば
- さほど練習しなくてもサッカーが上手い人もいる
その一方で、どんなに練習しても絶対に追いつけない人たちもいるのが現実。
才能による格差は否定できません。
2) 諸行無常
何かを諦めた人の中には、諦めてない人を自分の仲間に引きれようとする人がいます。
こうした人の根幹には、”人と自分は同じ”という平等願望があり世の中の不平等を受け入れられない心があるのかもしれません。
「諸行無常」という、仏教の基本的な考えがあります。

- 成功が長続きするとも限らないし
- 失敗したまま終わるとも限らない
何かを諦めたとしても、潔く次のフィールドで成功に向かって動き始めるべきなのです。
3) 不平等が活力になる
人々を平等原理主義に駆り立てるのは「かわいそう」と「羨ましい」の感覚だと思います。
- 自分よりかわいそうな人たちは救うべき
- いい思いをしてる人たちからはもっと取るべき
こうした圧力でいろいろ平均化していくことで、社会はある程度安定するでしょう。
とはいえ、「ほどほど」や「そこそこ」という言い方は結果論であり、ほどほどを目指すのはちょっと違う気がします。
過去は変えられないし未来のこともわからない。
不平等じゃないか!と叫ぶ前にまずは現実を直視すべきではないでしょうか。
『諦める力』の感想【しくじり先生が大事】

- 諦めなかった人が1000人いたとしても
- その中で成功するのはたった1人
みたいなことが現実ではよくあるはずです。
とはいえ多くのビジネス本は、たまたま諦めずに続けたたった1人の成功体験が書かれたりしています。
本当は、諦めなかったけど成功できなかった999人が「なぜ成功できなかったのか」を考えることの方が大事かもしれない。

『諦める力』とあわせて読みたいオススメ本3選

①『反応しない練習』(草薙龍瞬)
- 諦めるのはまだ早い
- 逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ
何かを諦めようとするとどうしても周囲からそんな声が出てくるはず。
そんな時、ムダに反応せず合理的に考えられるヒントをもらえる1冊です。
-
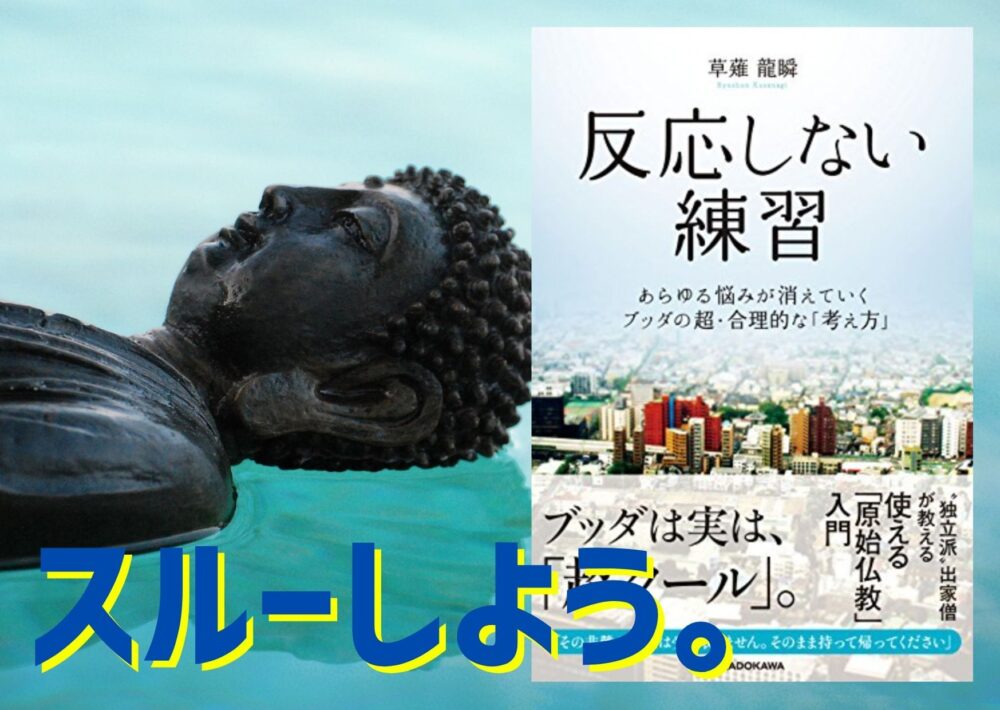
-
『反応しない練習』の要約・感想【合理的で実用的なブッダの思考法】
②『科学的な適職』(鈴木祐)
諦めるのは悪いことではない。
とはいえ、努力の方向を見誤っていてはどれだけ諦めても成功には近づきません。
『科学的な適職』は、幸福度を最大化する仕事を科学的根拠で分かりやすく学べる一冊です。
-
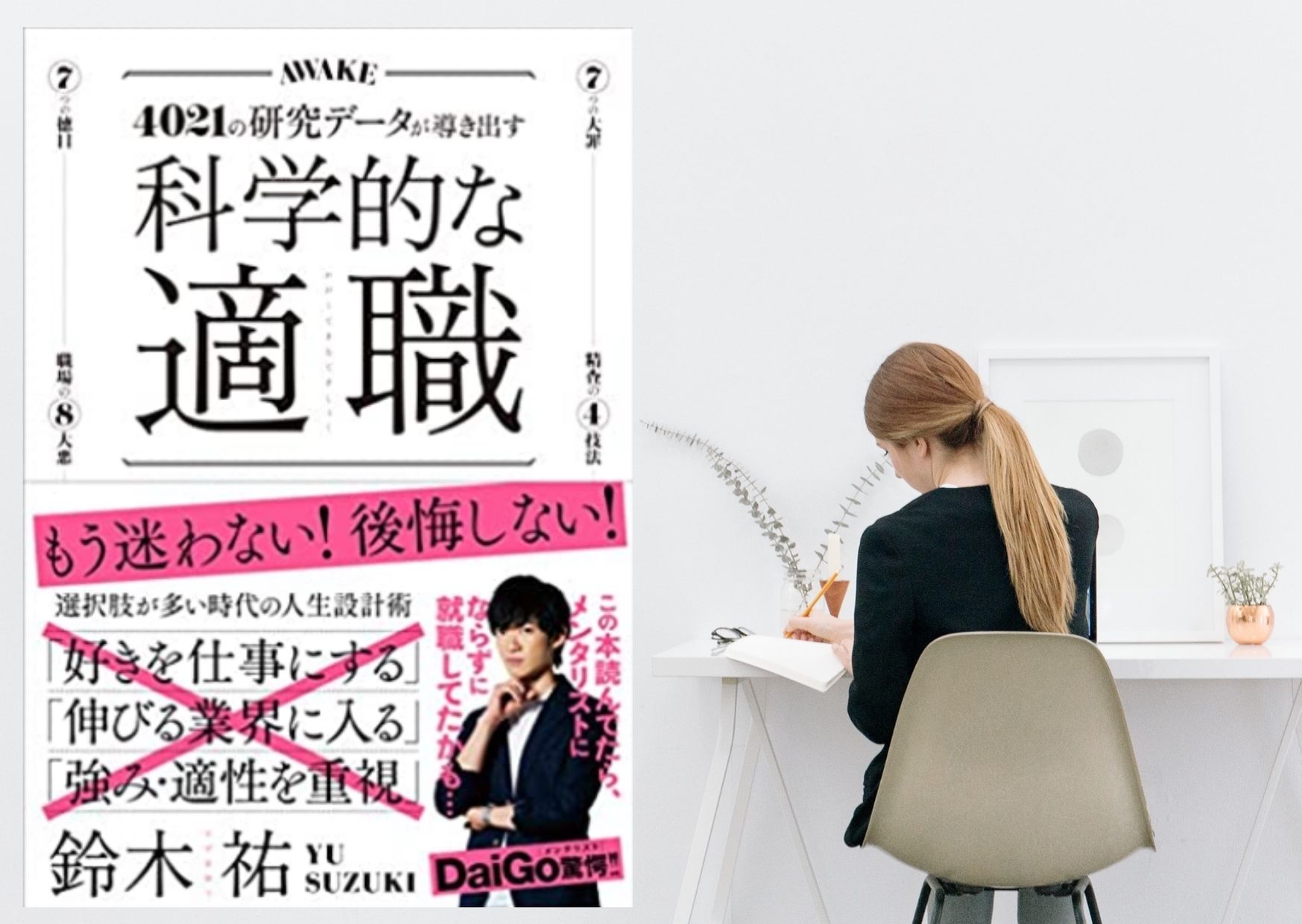
-
鈴木祐『科学的な適職』要約・感想【幸福度を最大化する仕事とは】
③『「やりたいこと」の見つけ方』(八木 仁平)
- 勝ちたいから努力するよりも
- あまり努力しなくても勝てるフィールドを探す方が
- 間違いなく勝率は上がる
為末さんは『諦める力』のなかでそのように述べていました。
努力を努力と思わないような「やりたいこと」を見つけられれば、圧倒的に成長できるんじゃないでしょうか。
-

-
『「やりたいこと」の見つけ方』の要約まとめ【自己理解のライザップ】
まとめ:前向きに、諦める
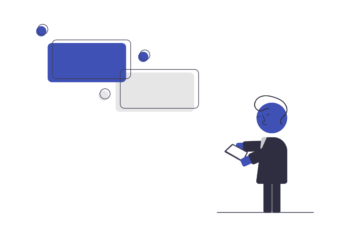
まとめます。
- 「手段」を諦めるのは目的を達成するための戦略
- 日本人独特の価値観に固執してはいけない
- 世の中は不平等という現実を直視すべき
「”成功”や”いま”という執着から逃れると人生が軽やかになる」と為末さんは述べています。
- 夢はかなう
- 可能性は無限だ
そういう考え方もありますが、”やめないこと”が目的になると、逆に自分の可能性を狭めることにもなりかねません。
「前向きに、諦める」
そんな心の持ち方を知りたい方は、いちど本書を手にとってみることをオススメします。
本書をフルで読みたい方は、下記2サービスがコスパ最強でオススメですよ!
- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited
の無料体験で読む
- AmazonオーディオブックAudible
の無料体験で聴く
-

-
【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?
今回は以上です。