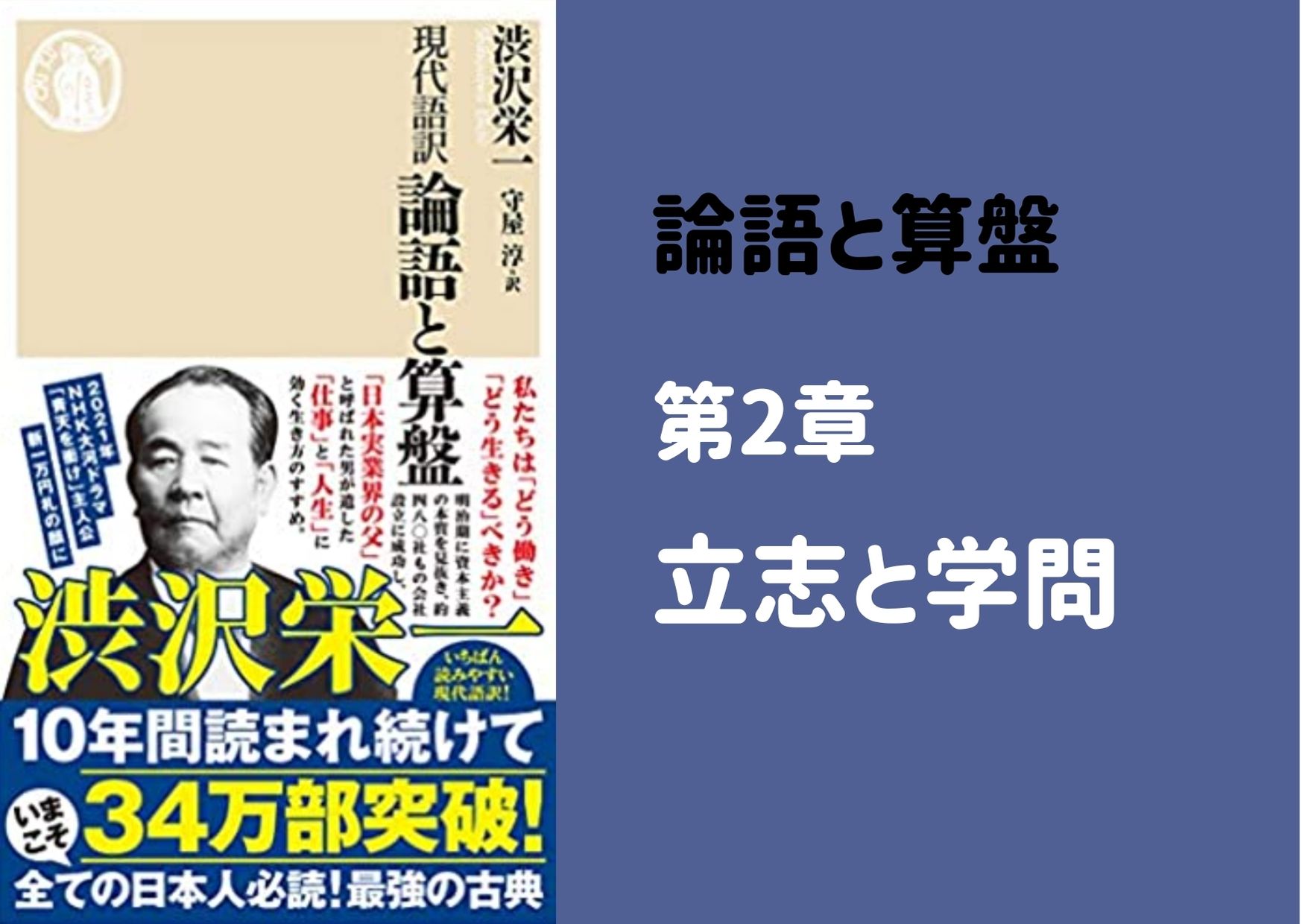日本実業界の父・渋沢栄一の著書『論語と算盤』の要約を、各章ごとにシリーズでお送りしております。

各章に順序性はないためどこから読んでも大丈夫ですが、前章をまだ読んでない方は上のリンクから各記事へジャンプできるのでよかったらどうぞ。
AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。
【論語と算盤】第2章「立志と学問」の要約
第2章のメニューは以下の通りです。
- 現在に働け
- 自ら箸を取れ
- 大きな志と小さな志との調和
- 立派な人間の争いであれ
- 社会と学問の関係
では順番に見ていきましょう。
①現在に働け
明治維新後はまだまだ士農工商の格差が大きく、武士には高レベルの教育が用意されてましたが、農工商への学問はほとんどありませんでした。
国の経済活動を盛んにしようにも、その知識や見識が備わっていない状況です。
なぜなら当時は、商人に高い知識など必要ないという考えが強かったからです。
「海外と交流していくためにはどうしても科学的知識が必要だ...」
渋沢がそう叫び続けた結果、ようやく才能と学問ともに備わった人材が輩出され始めました。
そして、そこからたった30~40年で日本も海外に負けないくらいに文明が発達しましたが、金儲けを優先する考えが強くなったことで今度は武士道や道徳がなくなっていったのでした。
- 国の経済は発展したけど
- 人格は退歩してしまった
そういう事です。
人々は、「富の増大」と「精神の向上」を両立するという強い信念を持たなければなりません。
②自ら箸を取れ
大きな仕事をしたいなら、力のある人に頼ってばかりじゃダメです。
なぜなら、そのような援助に救われるのは普通以下の人の話であり、本当に優れている人なら世間が放っておかないものだからです。
そもそも上の人間はお膳立てくらいはしてくれても、それを口に運んでくれるほどヒマじゃありません。
最終的には自分で箸を取らなきゃ大きな仕事はできないのです。
また、小さな仕事を”つまらない”と軽んじてはいけません。
どんなに些細な仕事も、それは大きな仕事の小さな一部です。
些細なことを粗末にする人間に大きな成功はやってきません。
「千里の道も一歩から」という昔の言葉があります。
豊臣秀吉も草履取りという小さな仕事を大切に勤め、自ら箸をとったからこそ関白まで昇り詰めたと言えます。
③大きな志と小さな志との調和
変化の激しい世の中において、社会風潮や他人の意見に流されていたら損してばかりです。
そうならないためにも、人生には一生貫けるような「大きな志」が必要です。
一生貫くためにも「大きな志」は慎重に考えましょう。
自分の長所短所を細かく比較考察しつつ、最も得意なところに向かって現実味のある志を定めるといいでしょう。
「大きな志」という根幹が定まったら、日々の変化に応じて「小さな志」を立てましょう。
「小さな志」は状況に応じて変化するものですが、「大きな志」と矛盾することがないようにしましょう。
両者は常に調和し一致しなければいけません。
- 大きな志は人生という建築の骨組みで
- 小さな志はその飾り
そんなイメージです。
と言いつつも、渋沢栄一自身の青年期は
- 武士になることを志したり
- 政治家として国政に参加することを志したり
- 実業家として商工業の発展を志したり
という感じで志がブレまくっていたそうです。
最終的には実業家という志を40年以上貫くわけですが、もっと若いうちから商工業に向かっていたらより結果が出ていたと言います。

④立派な人間の争いであれ
好んで他人と争う必要はありませんが、正しい道を進んでいくには争いは避けられないのも現実です。
人は誰でも「これだけは譲れない」というものは持つべきです。
それがないと、生き甲斐のない一生になることでしょう。
とはいえ、自分は争いは苦手なので円満な人になりたいという人もいるかもしれません。
それでもやはりどこかに角はあった方がいいです。円はすぐ転がってしまうので。

⑤社会と学問の関係
人情の陥りがちな欠点として、
成果をあせって大局を観ることを忘れ、目先のわずかな成功に満足してしまう。
という習性があります。
例えば以下のようなケースです。
- 地図で見るのと実地を歩いてみるのはまったく違ったり
- 机上での勉強と社会での現場経験はまったく違ったり
学問で事前にいくら備えても、実社会で不意を突かれることは多々あるもの。
学生の方々はそれを肝に銘じておくとよいでしょう。
【論語と算盤】第2章「立志と学問」のまとめ
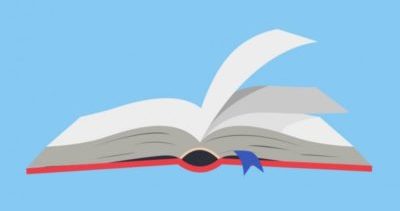
最後に、第2章「立志と学問」の要点をざっくり振り返ります。
- 「富の増大」と「精神の向上」の両立が大事
- 些細な仕事も自ら箸を取って真剣に取り組むべし
- 大きな志をベースに小さな志を立てよう
- 円満でも「ココは譲れない」という角はあった方がいい
- 学問と実社会は別物と心得よ
第3章はコチラからどうぞ!

-
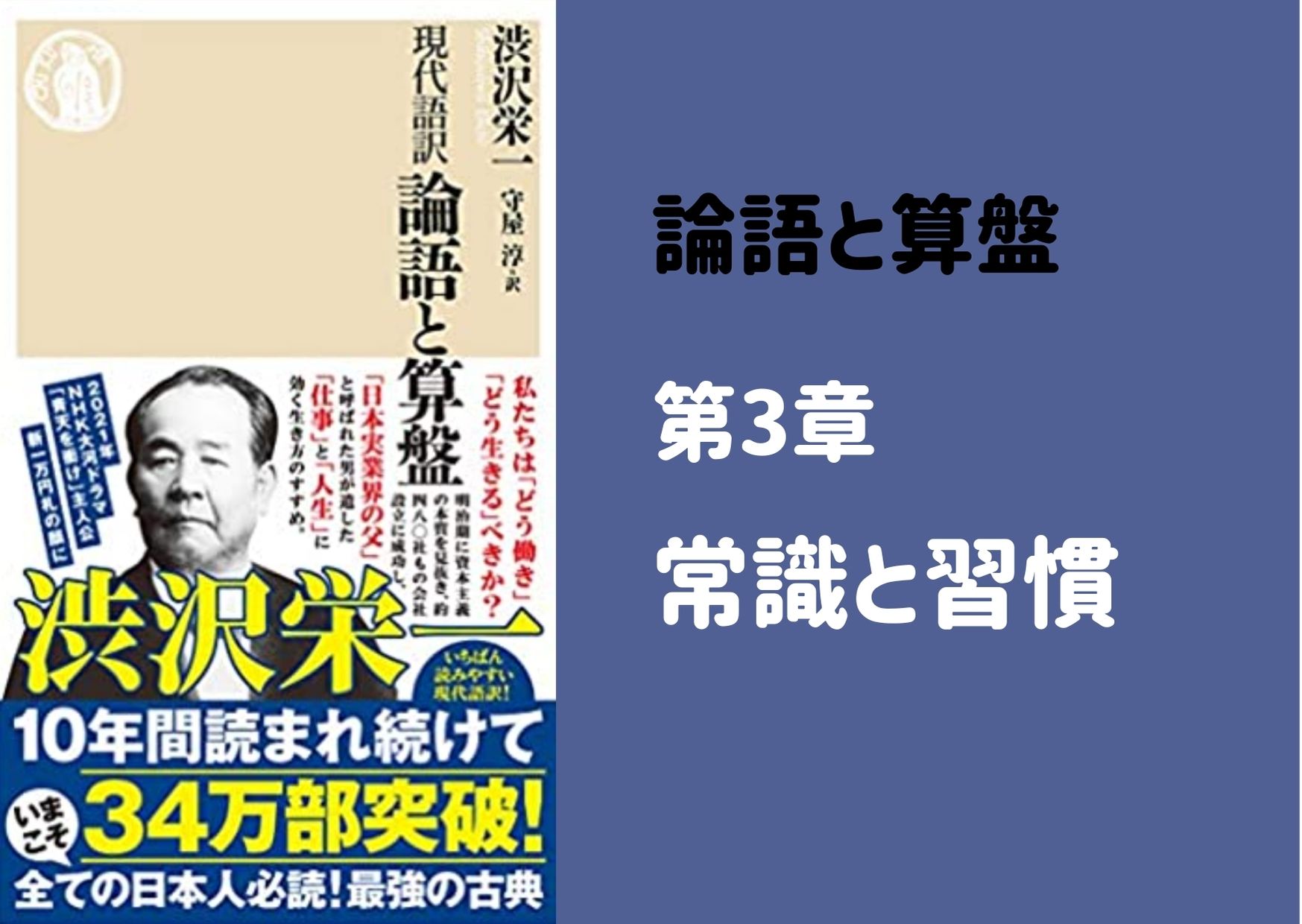
-
渋沢栄一『現代語訳:論語と算盤』第3章「常識と習慣」の要約まとめ
続きを見る
渋沢イズムをより深く知りたい方は本書をいちど手に取ってみることをオススメします。
マンガ版も要点が分かりやすくてオススメですよ。
AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。
-

-
【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?
続きを見る
今回は以上です。