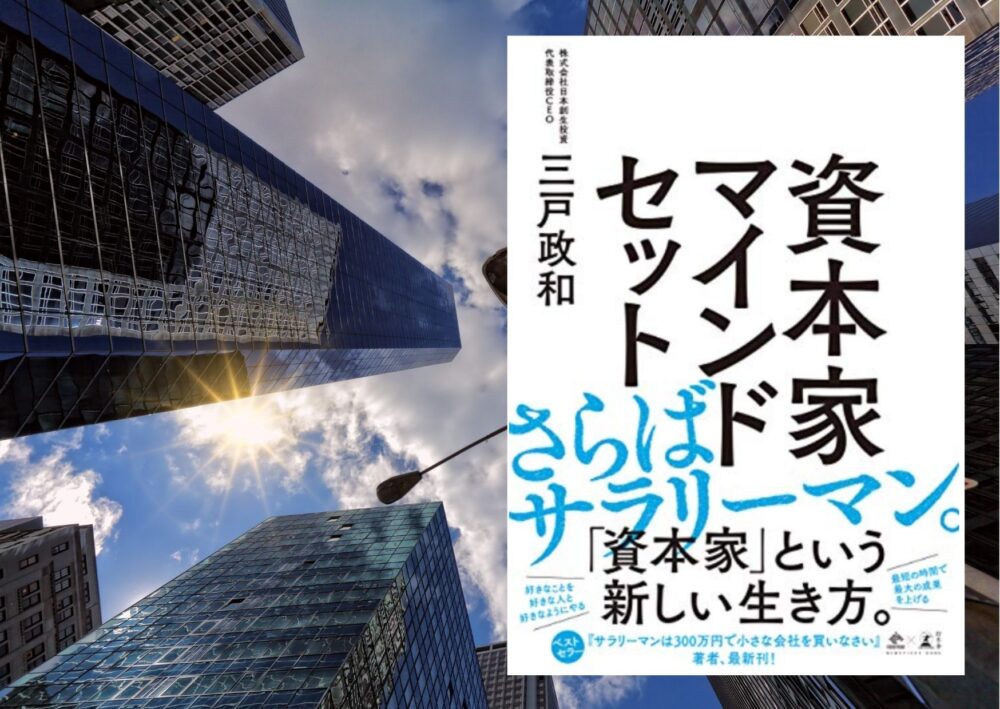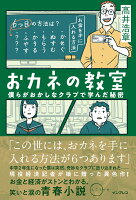この記事で分かること
- 資本家とは何か?
- サラリーマンは絶滅する?
- 資本家の仕事3原則
本書をフルで読みたい方は、下記2サービスがコスパ最強でオススメですよ!
- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited
の無料体験で読む
- AmazonオーディオブックAudible
の無料体験で聴く

それでは見ていきましょう。
もくじ
『資本家マインドセット』の基本情報
まずは『資本家マインドセット』の基本情報について見ていきます。
書名 :資本家マインドセット
著者 :三戸政和
出版月:2019/4/9
出版社:幻冬舎
定価 :¥1,540 (税込)
著者である三戸政和さんのプロフィールはコチラ。
株式会社日本創生投資代表取締役CEO。1978年兵庫県生まれ。同志社大学卒業後、2005年ソフトバンク・インベストメント(現SBIインベストメント)入社。ベンチャーキャピタリストとして日本やシンガポール、インドのファンドを担当し、ベンチャー投資や投資先にてM&A戦略、株式公開支援などを行う。2016年日本創生投資を投資予算30億円で創設し、中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行っている。
-Amazon著者情報より抜粋-
資本家は、お金からも労働からも自由な存在である。
なぜなら、資本主義のルールは資本家にもっとも有利に働くようになっているから。
サラリーマンと同じ労力で、数十倍・数百倍の結果を手にできるのが資本家です。

『資本家マインドセット』の要約

それでは、『資本家マインドセット』の内容を3つのパートに分けて要約していきます。
- 資本家とは何か?
- サラリーマンは絶滅する
- 資本家の仕事3原則
順番に見ていきましょう。
要約①:資本家とは何か?
1) 資本家は馬主みたいなもの?
著者の考える資本家とは、
- 会社の株を所有して
- その経営を自己のコントロール下に置く
それだけです。

と思うかもですが、それは投資家であり資本家ではありません。
なぜなら、0.00001%ほどの株主になっても自分の意向を経営に反映できないから。
資本家の生き方は、自分の手腕で会社の事業を成長させつつ利益を得ること。
また、現場で指揮を取る「経営者」とも違い日々の実務はそんなに多くないので、資本家はいくつもの会社を自分の支配下に置くことが可能になります。
競馬に例えるなら「馬主」です。
決して、騎手でも調教師でも馬券を買う人でもないということ。
2) 資本家は「お金を生む仕組み」をつくる
資本家の本質は「お金を生む仕組み」をつくることです。
「働く」という字は「人が動く」と書きますが、働くことの本質は自分が動くことではなく「何かを生み出すこと」にあると著者は主張します。
であれば、できるだけ少ない動きで効率よく働いた方が、より多くのものを生み出せることになります。
サラリーマンの働き方は基本的に「人(自分)が動く」です。
「自分の時間」という有限資産を切り売りしているため、稼ぎが爆発的に増えることはありません。
とはいえ、「お金を生む仕組み」もその内実は「人」であり、人が動かなければ富は生まれないのもまた事実。
だから資本家は、自分ではなく他人に動いてもらうのです。
3) 資本家マインドは「お金はただのツール」

という疑問もありますが、それは「資産家」であり「資本家」ではありません。

資産家は、お金を貯め込むことでお金を生むため、あまり積極的にお金を使うこともなく、お金そのものを目的とするようなスタイルになりがち。
一方で、資本家は稼いだお金を貯め込むことはせず、次の事業にどんどん使います。
そうやってやりたいことを次々に実現していくのが資本家にとっての幸福なのです。
そもそも、「資本家になろう=お金持ちになろう」ではありません。
なぜなら、お金は幸福のためのツールに過ぎないから。
お金それ自体には何の価値もないので、稼いだお金は次に何に使うかを考えるのです。

要約②:サラリーマンは絶滅する
1) サラリーマンはもはや「幕末の武士」
いまサラリーマンをしていて、最初から「サラリーマンになりたい!」と思ってた人はあまり多くないと思いますが、日本人の多くはサラリーマンです。
それはおそらく、サラリーマンという生き方が多くの人にとっての「ふつう」だから。
ですが、大量のサラリーマンが必要になったのは戦後の時代背景が主な要因であり、それは長い歴史のほんの一部でしかありません。
時代が変わり、ビジネスマンに求められるものが変われば、サラリーマンの存在意義も変わってくるものです。
江戸時代は武士の家に生まれれば武士になるのが「ふつう」でしたが、時代が変わり武士は消え去りました。
いまのサラリーマン制度は、終わりの近い「幕末の武士」のような段階にあると著者は述べています。
2) かつての日本は「小品種大量生産」
戦後の日本は大量のサラリーマンが必要でした。
それは、戦後の経済復興を支えたのが「小品種大量生産」だったから。
まだ物質的に貧しかったので、多様な商品を生産する必要はなく、みんなが同じ商品を大量に買い求めた時代でした。
そういう時代に企業が求めたのは
- 会社に忠誠心を持って
- 決まった給料で定年まで猛烈に働き
- ノルマが終わらなければ自ら残業してくれる
そんなサラリーマンという名の「兵隊」です。
そのためには、よその社風を知らないピュアな新卒が洗脳しやすかったわけですね。
3) 現代の主流は「多品種少量生産」
時代は変わり、いまは「多品種少量生産」です。
なぜなら、日々変化する多様な価値観に合わせて、次々と新しいサービスを提供するスピード感が求められるから。
そんな社会では、新卒一括採用でのんびり3年も育成していたら、あっという間に置き去りにされてしまいます。
何のスキルもない新卒の教育は、先行投資を回収するまでに時間がかかりすぎるわけです。
世界では、新しいプロジェクトを社内の人間だけで進めるのではなく、個別のプロジェクトごとに外部の人間も交えて特命チームを結成するのが主流です。

4) 「働き方改革」という名の「雇い方改革」
- 残業をなくそう!
- ワークライフバランスを大切に!
- リモートワークで自由な働き方を!
- 副業解禁!
働き方改革によって生まれたこうした声は、実は労働者側から出てきたものではなく、経営者たちから出てきたものです。
なぜなら、社員を会社に縛りつける「生涯サラリーマン制度」が、いまは経営者にとって足かせになっているから。
ITやロボットの発達で不要な人員が出てくるのは避けられませんが、「社員を減らしたい」と思っても簡単に削減できないわけです。

というかつてのスタンスから、

という、日本企業の経営者による「雇い方改革」なのです。
要約③:資本家の仕事3原則
1) お金と人に動いてもらう
いくつもの会社を抱える資本家は、自分が現場で動き回る社長業とは違い、「お金と人に動いてもらう」必要があります。
そのために重要なのは、誰がやっても同じ結果を出せるシステムづくりです。
業務を細分化して整理すれば、たいがいの仕事はマニュアル化できるので、いちいち現場に指示を出す必要はありません。

仕組み化ができないと、「業績UPには優秀な人材が必要だ」という発想になります。
たしかに優秀な人は1人で1億円の売上をあげることができるかもしれませんが、優秀な人がずっといるわけではありません。
それよりも、誰でも3000万円売り上げられる仕組みをつくって平均的な能力の人を3人雇った方が再現性も継続性もあり、事業規模も拡大しやすいのです。
また、お金と人に動いてもらうためには、仕組み化のあとに以下3つが必要と言われています。
- 丸投げ力
→「人に任せる」メンタリティが重要 - 60点でOKとする
→小さな失敗を失敗と思わない - オープンな情報共有
→「聞いてない」という人がいると二度手間
2) バランスシートで儲ける
企業の財務諸表で多くの人が気にするのが「損益計算書」です。
損益計算書には、1年間の売上から費用を差し引いた数字が書かれています。
- プラスなら黒字
- マイナスなら赤字
その年、会社が儲かったのかがわかります。
しかし、企業にはもうひとつ「貸借対照表(バランスシート)」という重要な財務諸表があります。
バランスシートでわかるのは、その時点における会社の資産・負債・純資産の状況です。
資本家は、バランスシートを見つつ会社の「資産価値」も考えなくてはいけません。
例えば、ヨーロッパのある高級ブランドは赤字になるとわかっていても新規店舗を出店することがあるそうです。
なぜなら、店舗の敷地のほかに、その周辺の土地もまとめて買っているから。
高級ブランドの新店舗が登場することで、周辺の地価が上がることを見越しているわけです。
資本家の仕事は、会社に利益を出させることだけではなく、会社を使って利益を出すということ。
3) ポートフォリオを組む
「ポートフォリオを組む」は、投資家が株式や債券などに分散するリスク管理と同じです。
「卵をひとつのカゴに盛るな」という有名な格言がありますが、ひとつのカゴに全ての卵を入れてたら、カゴが壊れたときに卵が全滅するということ。
会社経営においても、ひとつの事業に依存するのは危ういわけです。
例えば、ミクシィはSNSとして一世を風靡していましたが、TwitterやFacebookなどの登場によって利用者が激減し、一時は死に体となっていました。
大地震で、たったひとつの工場が壊滅してしまう可能性もあります。
自然災害のリスクは避けようがないため、ポートフォリオによるリスク分散は不可欠なのです。
リスク分散の観点で見ると、サラリーマンは所属する会社ひとつに依存し、まったくポートフォリオが組めていません。
副業などを持ちつつ、収入源を分散させることも必要かもしれません。
『資本家マインドセット』とあわせて読みたいオススメ本3選

①『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』(橘玲)
橘玲さんのベストセラー『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』です。
黄金の羽根とは「制度の歪みから構造的に発生する”幸運”」で手に入れたものに大きな利益をもたらすとされています。
本書のそれは、法人をつくり合法的に税金を払わないこと。
道徳的にどうなん?と思うかもですが、
- 経済的に成功するためには、経済合理的でなくてはならない
- 国家は神聖なものでも、崇拝や愛情の対象でもなく、人生を最適設計するための道具
という著者の主張は一理あるんじゃないでしょうか。
-
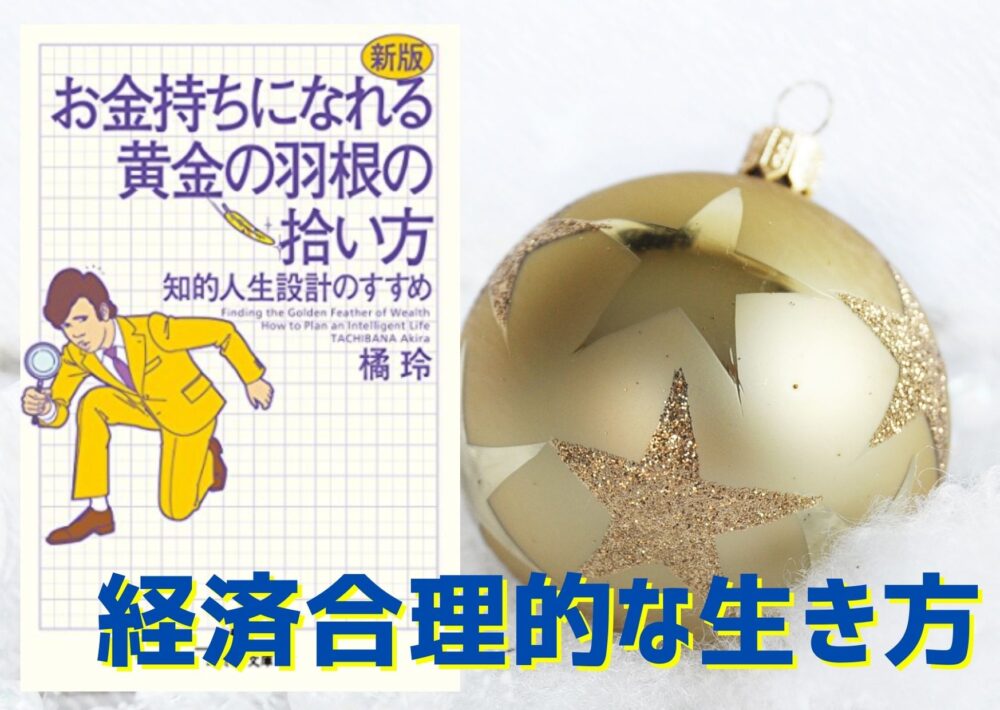
-
橘玲『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』の要約【経費という魔法】
②『みんなが欲しかった!FPの教科書3級』(滝澤ななみ)
「FP技能士3級」という資格勉強のテキストですが、税金や社会保険などの基本知識が体系的にまとめられているので、これ1冊でお金の教養が身に付きます。
資格を取る取らないに関係なく、日本で生活するなら読むべき1冊です。

バランスシートや事業所得の考え方など、資本家マインドに役立つ内容が盛り沢山です。
-

-
FP資格は意味ない?筆者が実感したメリット6つ【FP2級保持】
③『おカネの教室』(高井浩章)
お金儲けは悪いこと、金に執着するのは卑しいといった風潮がまだまだ根強い日本ですがお金の話は本来「楽しい」もの。
- 面白い物語を読んでるだけで
- お金や経済の仕組みがわかる本
を3人の子供たちに読ませたいと考えた著者が、7年かけて家庭内連載していた小説を書籍化したのが本書です。
父が娘に送る「学べる小説」で経済に対する理解を深めてみましょう。
-
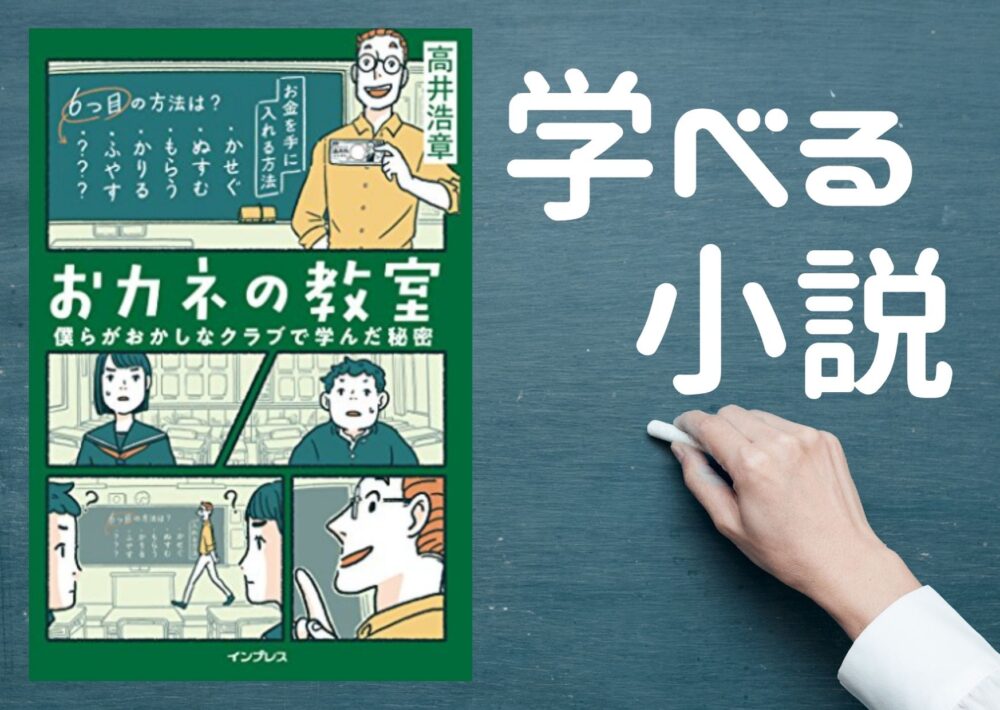
-
『おカネの教室』の要約まとめ【父が娘に送る「学べる小説」】
まとめ:最短の時間で最大の成果を上げる

まとめます。
資本家とは何か?
- 馬主みたいなもの
- お金を生む仕組みをつくる
- お金はただのツール
サラリーマンは絶滅する?
- もはや幕末の武士
- 小品種大量生産から多品種少量生産へ
- 「働き方改革」という名の「雇い方改革」
資本家の仕事3原則
- お金と人に動いてもらう
- バランスシートで儲ける
- ポートフォリオを組む
「資本家=労働者から搾取する人」というイメージを持っている方も少なくないかもしれません。
とはいえ、最短の時間で最大の成果を上げるための考え方は、我々いちサラリーマンにも必要なマインドセットであることは間違いありません。
「誰もが脱サラして会社を買うべき」とは思いませんが、サラリーマンとして生きてくうえでも参考になる点が多い1冊。
資本家という生き方を垣間見たい方は、いちど本書を手にとってみることをオススメします。
本書をフルで読みたい方は、下記2サービスがコスパ最強でオススメですよ!
- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited
の無料体験で読む
- AmazonオーディオブックAudible
の無料体験で聴く

今回は以上です。