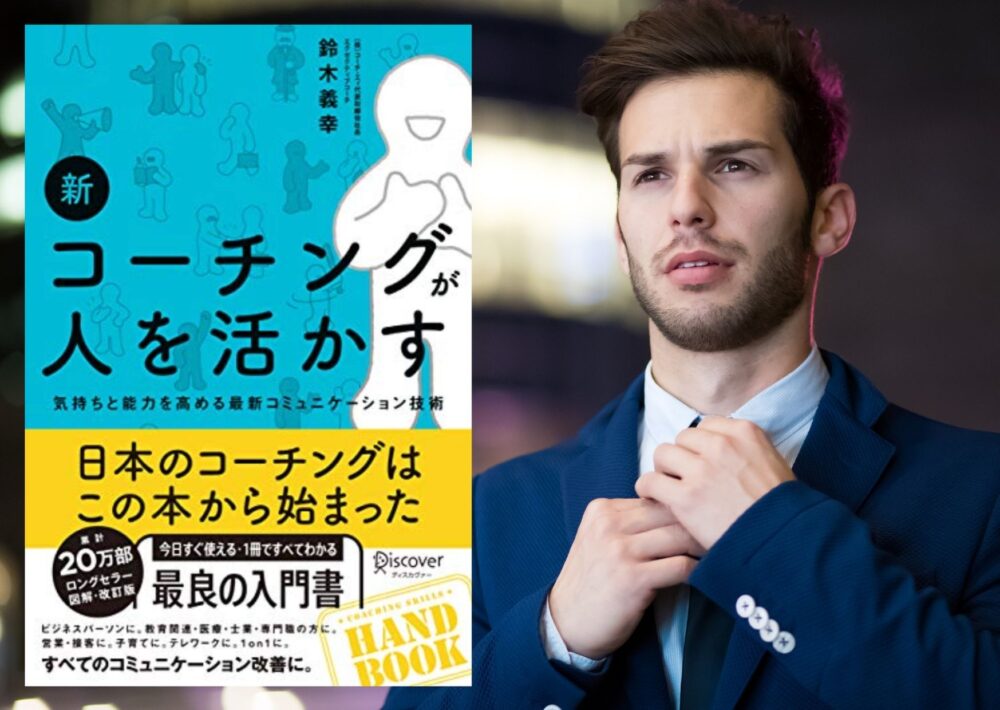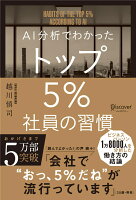この記事で分かること
- 相手と信頼関係を築く方法が分かる
- 視点・切り口の変え方が分かる
- 組織に対話を引き起こす方法が分かる
本書をフルで読みたい方は、下記2サービスがコスパ最強でオススメですよ!
- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited
の無料体験で読む
- AmazonオーディオブックAudible
の無料体験で聴く

それでは見ていきましょう。
もくじ
『コーチングが人を活かす』の基本情報
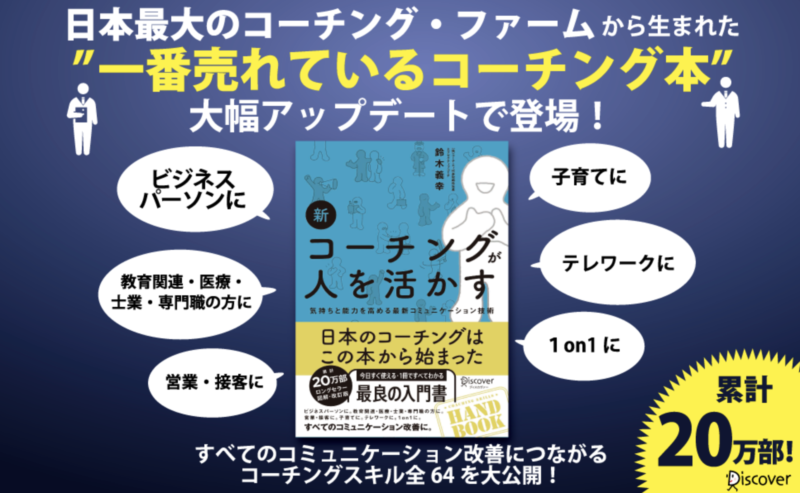
Amazon書籍ページより引用
まずは『コーチングが人を活かす』の基本情報について見ていきます。
書名 :新 コーチングが人を活かす
著者 :鈴木義幸
出版月:2020/6/26
出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
定価 :¥1,760 (税込)
著者である鈴木義幸さんのプロフィールはコチラ。
株式会社コーチ・エィ取締役社長。チーフエグゼクティブコーチ。国際コーチ連盟マスター認定コーチ。株式会社マッキャンエリクソン博報堂(現・株式会社 マッキャンエリクソン)に勤務後、渡米。帰国後、コーチ・トゥエンティワンの設立に参画。企 業向けに管理職を対象とするコーチングのトレーニングを行うほか、経営トップ、経営層へのエグゼクティブ・コーチングを多数実施、組織変革の支援を手がける。
-Amazon著者情報より抜粋-
20年前、「最良のコーチング入門書」としてロングセラーとなった本書がアップデートされました。
コーチングの必要性には3つの理由があると言われています。
- 正解を見つけにくい課題の増加
- 多様性の拡大
- イノベーションの必要性

『コーチングが人を活かす』の要約
それでは、『コーチングが人を活かす』の内容を3つのパートに分けて要約していきます。
- 相手と信頼関係を築く
- 視点・切り口を変える
- 組織に対話を引き起こす
順番に見ていきましょう。
要約①:相手と信頼関係を築く
1) あいづちを意識して磨く
あなたは普段どのくらいあいづちを意識してますか?
- 声のトーン・大きさ
- 顔の表情
- タイミング
- あいづちの言葉
相手の話をちゃんと聞いていたとしても、あいづちひとつで人は話したくなったり、話す気がなくなったりするものです。

- 録音するなり
- 親しい人に聞いてみるなりして
まずは、「自分がどんなあいづちを打っているか」という客観的な情報に触れてみましょう。
2) 「4つのタイプ」を知る
人はそれぞれ違うという前提で、相手を理解しつつ、タイプに応じた接し方が必要です。
コーチングにおいては、対人関係上の特徴として4つのタイプに分けて考えます。
- コントローラー・タイプ
→行動的で自分が思った通りに進めることを好む。
こちら側でコントロールしないようにすることが大切。 - プロモーター・タイプ
→人と一緒に活気のあることをするのを好む。
否定的なアプローチをしないことが大切。 - アナライザー・タイプ
→物事を客観的に捉え分析するのが得意。
自分の気持ちを表に出させるのは逆効果。 - サポーター・タイプ
→他人の気持ちに敏感で気配り上手。
承認欲求か強いので、十分な評価を与える必要がある。
自分と相手のタイプを知りつつ、お互いのいい部分を最大限に活用する方法を考えましょう。
3) 「You」ではなく「I」で褒める
コーチングにおいて、相手を褒めたり承認することはとても重要です。
とはいえ、そのスタンスは「You」と「I」の2つに分かれます。
「You」のスタンス
- よくやった!
- やればできるじゃないか
- 優秀だね
など、「あなたはこうだ」と伝えること。
「I」のスタンス
- 君が頑張ってるおかげで僕もやる気が出るよ
- 君のプレゼンは安心して見てられるよ
など、「相手が自分にどう影響を与えたか」を伝えること
「You」の褒め方は人によってストレートに受け取りにくい面もありますが、「I」の褒め方はこちら側の感想なので否定しようがなく、言われるととても嬉しいものです。
「You」で褒めそうになったら、いちど立ち止まって「I」の承認に変えてみましょう。
要約②:視点・切り口を変える
1) ストーリーで語る
- 人生とは・・
- 仕事とは・・
「AとはBである」的な一般論を聞かされるのは苦痛でしかありません。
なぜなら、一般論を無防備に受け入れたら人生がどんどん窮屈になるから。
「AとはBである」ということを相手に伝えたかったら、そこに具体的な「ストーリー」を加えるようにしましょう。
- 自分の体験談であったり
- 知人のエピソードだったり
- 本で読んだストーリーでも構いません
ストーリーに乗せることで、「AとはBである」を実証する事実を示すことができ、相手の頭にも残りやすくなります。
2) 「なぜ」を説明する
- ルールだから
- 自分の時代がそうだったから
- そういうものだから
かつては通じたかもしれないこのような指示が、現代では通用しません。
小さいことでも「なぜそれをするのか」という意味や目的を伝える必要があります。
とはいえ、すべてをていねいに説明していては相手のメンタルにも悪影響です。
- 説明し過ぎもダメ
- 不条理ばかりでもダメ
両社のバランスをいかにとるかが、コーチの腕の見せどころかもしれません。
3) 逆にコーチングしてもらう
普段は”コーチングする側”の人も、敢えて逆に”コーチングされる側”になってみることをオススメします。
なぜなら、役割を入れ替えることで、視野が広がったり別の視点を持てるから。
部下に「俺はどうすればもっといい上司になれると思う?」と聞いてみるのです。
- コーチングを受ける人だけでなく
- コーチングする人も成長できる
ということ。
要約③:組織に対話を引き起こす
1) 異論反論を大切にあつかう
「信用」と「信頼」は似て非なるものです。
- 信用は理性的な判断
- 信頼は感情的な結びつき
そして、”感情的な結びつき”であれば「信頼」と「信仰」も共通しますが、両者もまた似て非なるもの。
- 信頼は異論反論を許すけど
- 信仰は異論反論を許さない
つまり、異論反論を許し合ってこそ本当の信頼が築かれるということです。
「会議で意見が出ない」という悩みがよく出ますが、それは”自由に発言できる安心感”が足りないのです。
「異論反論を言っても大丈夫」という信頼があれば、安心感が生まれ活発な意見が飛び交うでしょう。
2) 「横の対話」に一歩踏み出す
組織には「縦の対話」と「横の対話」があります。
- 縦の対話・・・上司-部下などの対話
- 横の対話・・・部門を超えての対話
縦の対話はできても、横の対話が苦手な人は少なくありません。
なぜなら、「話す」というのは、”相手に批判・否定されるかもしれないリスク”があるものだから。
- ”ポジション”に守られて話す「縦の対話」はいいけど
- 防御が薄くなる「横の対話」は避けたい
そういうことです。
「横の対話」のコツは、自分の利益は一旦置いといて、相手のために話すことです。
最初は「なんでこんな譲歩しなきゃいけないんだ」と不満かもしれませんが、数を重ねるごとに信頼感が醸成されていきます。
『コーチングが人を活かす』の感想
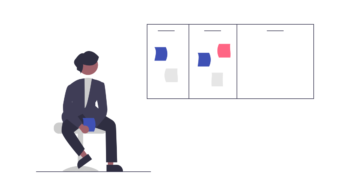
ひとつ一つの項目は”当たり前”と感じるかもですが、いざ自分の行動と照らし合わせるとできてないことは結構あるはず。
どの項目も4ページずつにスッキリまとめられているので、気になるところだけ小分けに読むこともできて便利ですね。
個人的には「逆にコーチングしてもらう」という視点は新たな気づきでした。
- 「教える」「指示する」というスタンスではなく
- 「理解し行動できるよう促す」ことが
重要なポイントだと思います。
『コーチングが人を活かす』とあわせて読みたいオススメ本3選

①『たった1%のリーダーのコツ』(河野英太郎)
- リーダーはメンバーより仕事ができるべき
- メンバーがなかなか育たない
- メンバーが指示どおり動いてくれない
そんな風に思うことはありませんか?
リーダーに求められる能力は決して特別なものではありません。
むしろ、「コツ」さえ掴めばどんな人でもリーダーになれるというのが著者の主張。

-
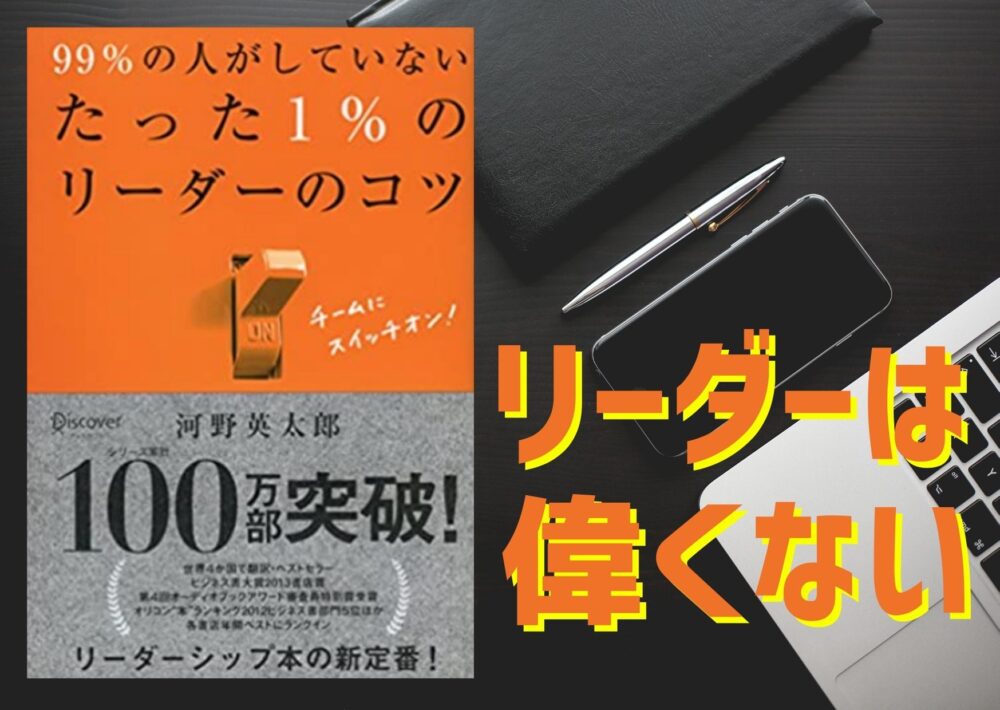
-
『たった1%のリーダーのコツ』の要約【リーダーはただの「役割」】
②『コンサル1年目が学ぶこと』(大石哲之)
職種や業界を問わず今後も役立つ普遍的なベーシックスキルをとても分かりやすく学べる良書です。
決してコンサル担当者だけのものではなく、すべてのビジネスパーソンにオススメできます。

-
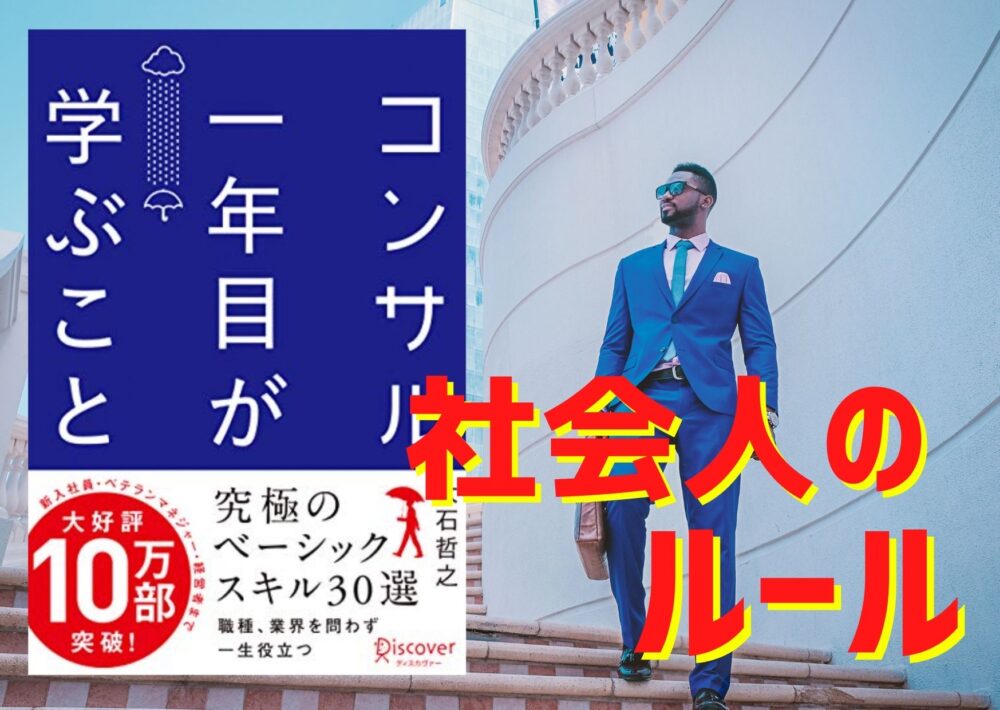
-
『コンサル1年目が学ぶこと』の要約【ビジネスマンの普遍的スキル】
③『トップ5%社員の習慣』(越川慎司)
効率よく成果を出す人にはシンプルな共通点がありました。
18,000人のビジネスパーソンに対して、
- 定点カメラ
- ICレコーダー
- 対面ヒアリング
などを通じて、トップ5%社員の思考や行動をAI分析した”働き方の結論”です。
-
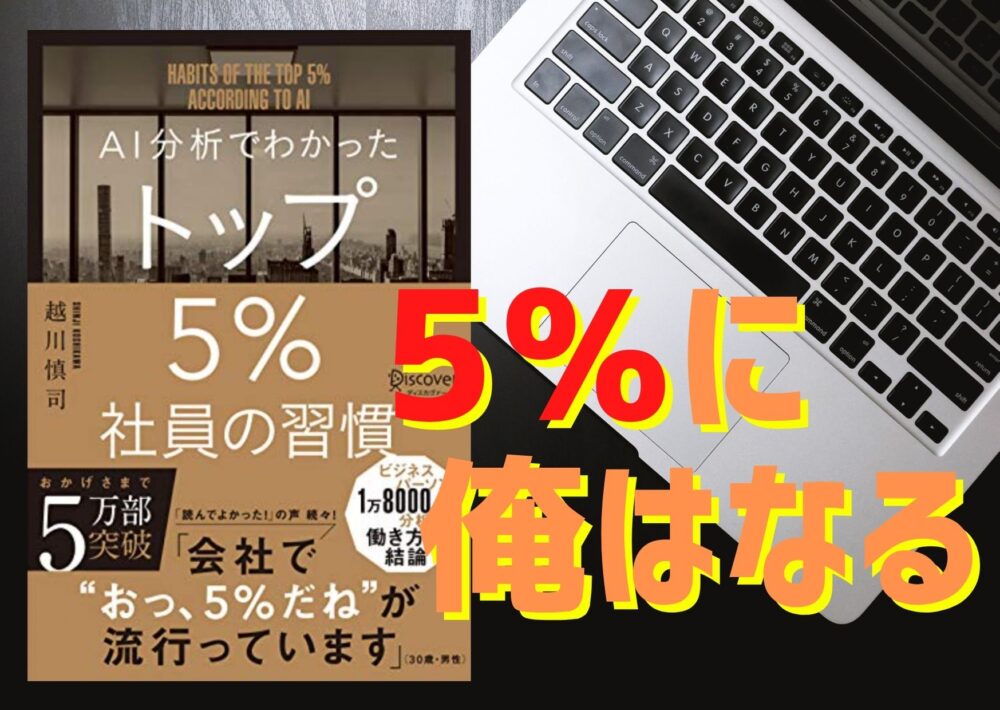
-
『トップ5%社員の習慣』の要約・感想【ゴールに向かって即行動】
まとめ:コーチングで主体的な人材をつくる
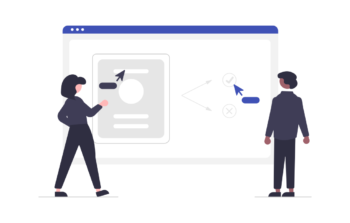
コーチングの本質は、”未来を創り出す主体的な人材をつくる”こと。
- 目の前の人の主体性に働きかけ
- 未来に向けて飛躍するように
- いかに自分のコミュニケーションを使うか
それがコーチングの目指すところ。
この記事で紹介できたコツはほんの一部です。本書では全部で7つのレッスンがまとめられています。
- 相手と自分の発見をうながす
- 相手と信頼関係を築く
- 目標達成に目を向ける
- 視点・切り口を変える
- 主体的な行動をうながす
- コーチングの達人に向けて
- チーム・組織に対話を引き起こす
コーチングで人を活かしたい方は、いちど本書を手にとってみることをオススメします。
無料で楽しみたい方は、以下2つの方法がコスパ最強でオススメですよ。
- 電子書籍のサブスクKindle Unlimited
の無料体験で読む
- AmazonオーディオブックAudible
の無料体験で聴く
-

-
【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?
今回は以上です。