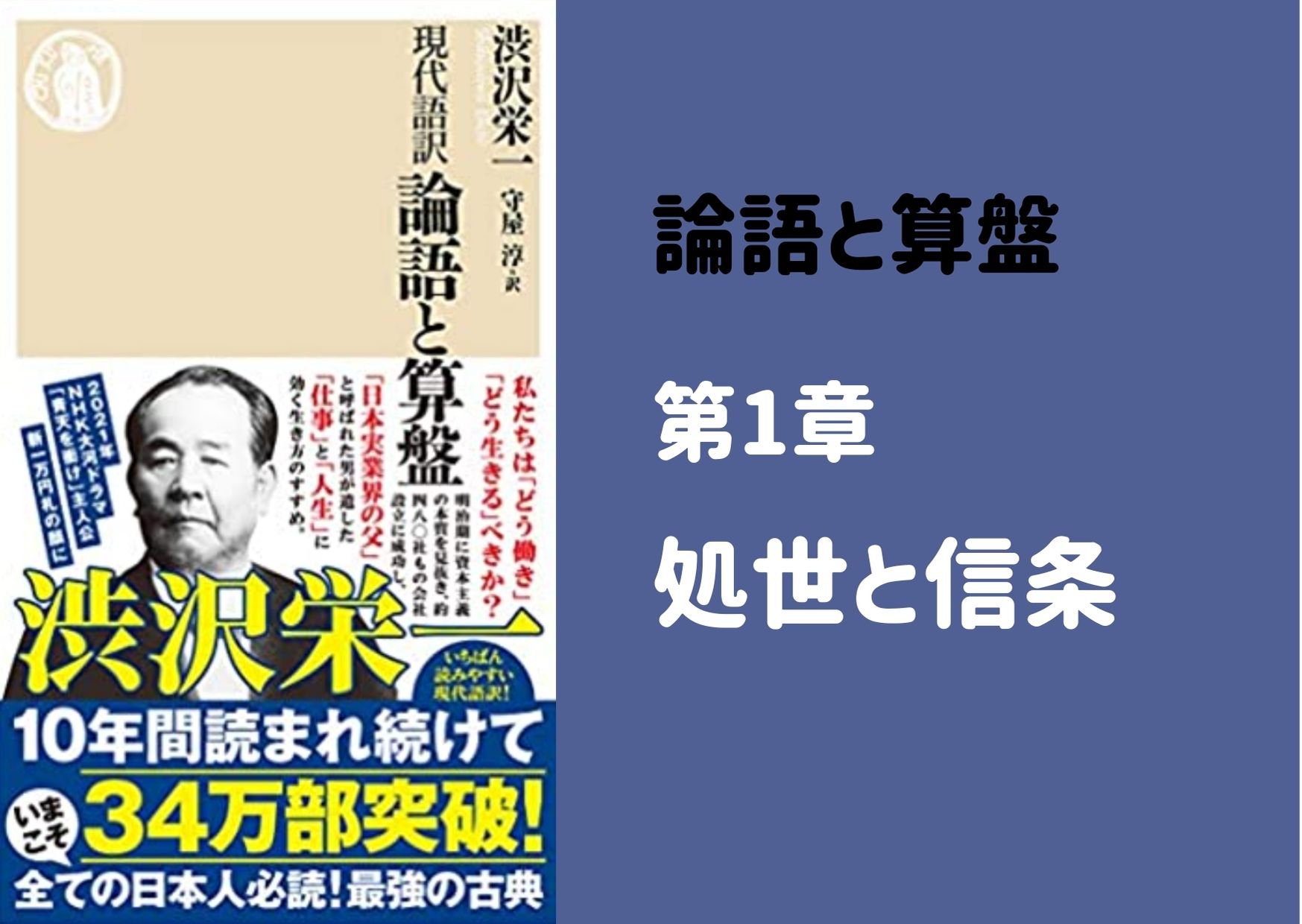そんな疑問に答える記事です。
『論語と算盤』は、”日本実業界の父”とも言われる渋沢栄一が生涯を通して貫いた「経済と道徳は調和するべき」という経営哲学をまとめた一冊になっています。
経営哲学とはいえ、その内容は「いつの時代も変わらぬ人としての正しい生き方」を示しており、経営者に限らず全ての人間の原点とも言える考え方です。

それでは行ってみましょう。
AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。
もくじ
『論語と算盤』の基本情報
まずは『論語と算盤』の基本情報について見ていきます。
なお、『論語と算盤』は複数の出版社から発行されていますが、当ブログでは守屋淳さん翻訳の『現代語訳 論語と算盤』に準じて話を進めていきます。

書名 :現代語訳 論語と算盤
著者 :渋沢栄一 (翻訳・守屋淳)
出版月:2014/1/10
出版社:筑摩書房
定価 :¥902 (税込)
『論語と算盤』は渋沢栄一の講演内容を抜粋して書籍化しているものです。ときどき似たような趣旨の話が別の章で出てくる事もありますが、そこはご理解ください。
ご存じの方も多いでしょうが、著者である渋沢栄一さんのプロフィールはコチラです。
江戸時代末期に農民から武士(幕臣)に取り立てられ、明治政府では大蔵少輔事務取扱となり大蔵大輔・井上馨の下で財政政策を行った。退官後は実業家に転じ、第一国立銀行や理化学研究所、東京証券取引所といった多種多様な会社の設立・経営に関わり、二松學舍第3代舎長(現・二松学舎大学)を務めた他、商法講習所(現・一橋大学)、大倉商業学校(現・東京経済大学)の設立にも尽力し、それらの功績を元に「日本資本主義の父」と称される。また、『論語』を通じた経営哲学でも広く知られている。
-Wikipediaより抜粋-
- 日本資本主義の父
- 2021大河ドラマ『晴天を衝け』主人公
- 2024年~新1万円札の顔
ということで、いま大注目の渋沢先生です。
本書は以下の全10章で構成されています。
どれも大事な話ばかりなので、1記事/1章で要約していきます。(見たい章をクリックすると該当記事へジャンプします)
まずは第1章から見ていきましょう。
【論語と算盤】第1章「処世と信条」の要約

第1章のメニューは以下の通りです。
- 「論語」とソロバンは、はなはだ遠くて近いもの
- 士魂商才
- 論語はすべての人に共通する実用的な教訓
- 争いは良いのか、悪いのか
- 立派な人間が真価を試される機会
- 蟹穴主義が肝要
- 得意なときと失意のとき
では順番に見ていきましょう。
①「論語」とソロバンは、はなはだ遠くて近いもの
「論語」は、中国の思想家だった孔子の教えを弟子たちがまとめた書物で、現代の日本人にも通ずる道徳のお手本とも言える重要な書物です。
一方でソロバンは電卓のアナログ版で、「経済」を意味します。
道徳と経済はかけ離れたものと思われがちですが、
- ソロバンは論語によってできており
- 論語もソロバンによって本当の経済活動と結びつく
実はとても近いものなのです。
国の富が形になるには、大きな欲望を抱いて経済活動を行ってやろうという気概とともに実業界が力を持つ必要があり、その基盤は社会の基本的な道徳に他なりません。
②士魂商才
- 士魂・・・武士の精神
- 商才・・・商人の才覚
世の中で自立していくためには武士のような精神が必要だが、それだけじゃ経済が発展しない。
そのため、士魂とともに商才も必要なのだ、という事です。
そして、士魂も商才も『論語』で養えると言います。
徳川幕府が200年以上も続いたのも、徳川家康のベースに論語があったからと言えるでしょう。
③論語はすべての人に共通する実用的な教訓
渋沢栄一が官僚から実業界に転身した際、同僚からこんな事を言われます。
「金銭に目がくらんで、官職を去って商人になるなんて実に呆れる...」
この頃はまだまだ”官尊民卑”・”士農工商”の意識が強く、金儲けは卑しいという考えすらありました。
ですが渋沢は、
- 金銭を卑しんでいては国家は立ち行かない
- 官だけが尊いわけじゃない
と主張します。
そして、論語を貫きつつ一生商売をやると決心したそうです。明治6年のことでした。
論語は決してむずかしい学問ではなく広く世間に効き目がある。士農工商に関わらずすべての人が論語を学ぶべきだというのが渋谷の考えでした。
④争いは良いのか、悪いのか
世間には、いかなる場合でも争いはよくないと説く者もいますが、果たしてホントにそうでしょうか。
もちろん理由もなく争うようなことはしませんが、国家が健全に発展していくためには常に外国と争ってこれに勝ってみせるという意気込みも必要です。
そしてその意気込みは国家に限らず一個人においても同じことが言えます。
例えば後輩教育なら、
- 何をしても穏やかな先輩より
- すぐに怒るような怖い先輩の方が
身が引き締まりやすく後輩の利益になるものです。
⑤立派な人間が真価を試される機会
人生には多かれ少なかれ逆境に立たされることがあるものです。
とはいえ、大事なのはそれが
- 人の作った逆境なのか
- 人にはどうしようもない逆境なのか
をまずは区別して策を立てるべきです。
そして人間の真価が試されるのは”人にはどうしようもない逆境”に立たされた時です。
その時は、現状を受け入れつつ「どんなに悩んでもそれが天命だから仕方ない」といい意味で”あきらめ”の考えを持つことで平静さを保てます。
ところがこれを”人が作った逆境”と解釈し自分で何とかしようとすると無駄に苦労を増やすだけで何も達成できない結果が待っています。
一方で”人の作った逆境”に立たされた場合は、ほとんど自分のやったことの結果なので反省しつつ悪い点は改めるしかありません。
⑥蟹穴主義が肝要
蟹は自分の甲羅の大きさに合わせて穴を掘るのだそうです。
要するに蟹穴主義とは、「身の丈をわきまえましょう」という意味です。
なぜなら、自分の力を過信して身の丈を超えた望みを持って進むととんだ間違いを引き起こしがちだからです。
とはいえ、意欲的に新しいことに挑戦する気持ちも忘れてはいけません。
- 身の丈をわきまえつつ
- 新しいことにも挑戦する
大事なのは「バランス」ということ。
また、喜怒哀楽もバランスをとる必要があります。

⑦得意なときと失意のとき
災いの多くは得意なとき(調子に乗ってるとき)に起こるもの。
- 得意なときも調子に乗らず
- 失意のときも落胆せず
いつも同じ心構えで道理を守り続けるのが大切です。
得意なときは些細なことが気にならなくなりますが、それが後々に大きなことに発展しがちなので気をつけましょう。
とはいえ、些細なことを気にしすぎて精神をムダに疲れさせる必要もありません。
大小に関わらず、その性質をよく考慮しつつ相応しい対処を心掛けるべきです。
【論語と算盤】第1章「処世と信条」のまとめ
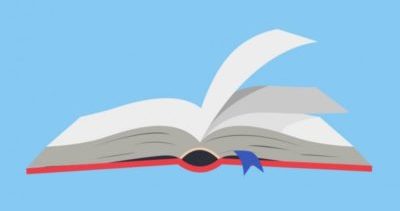
最後に、第1章「処世と信条」の要点をざっくり振り返ります。
- 道徳を基盤にした経済活動が国を豊かにする
- 論語で武士の精神と商人の才覚を掛け合わせるべし
- 士農工商に関わらずすべての人が論語を学ぶべきだ
- 国家も個人も競争心が必要
- 人間の真価が試されるのは”どうしようもない逆境”
- 身の丈をわきまえつつ新たな挑戦も
- 災いは調子に乗ってるときに起こりがち
第2章はコチラからどうぞ!

-
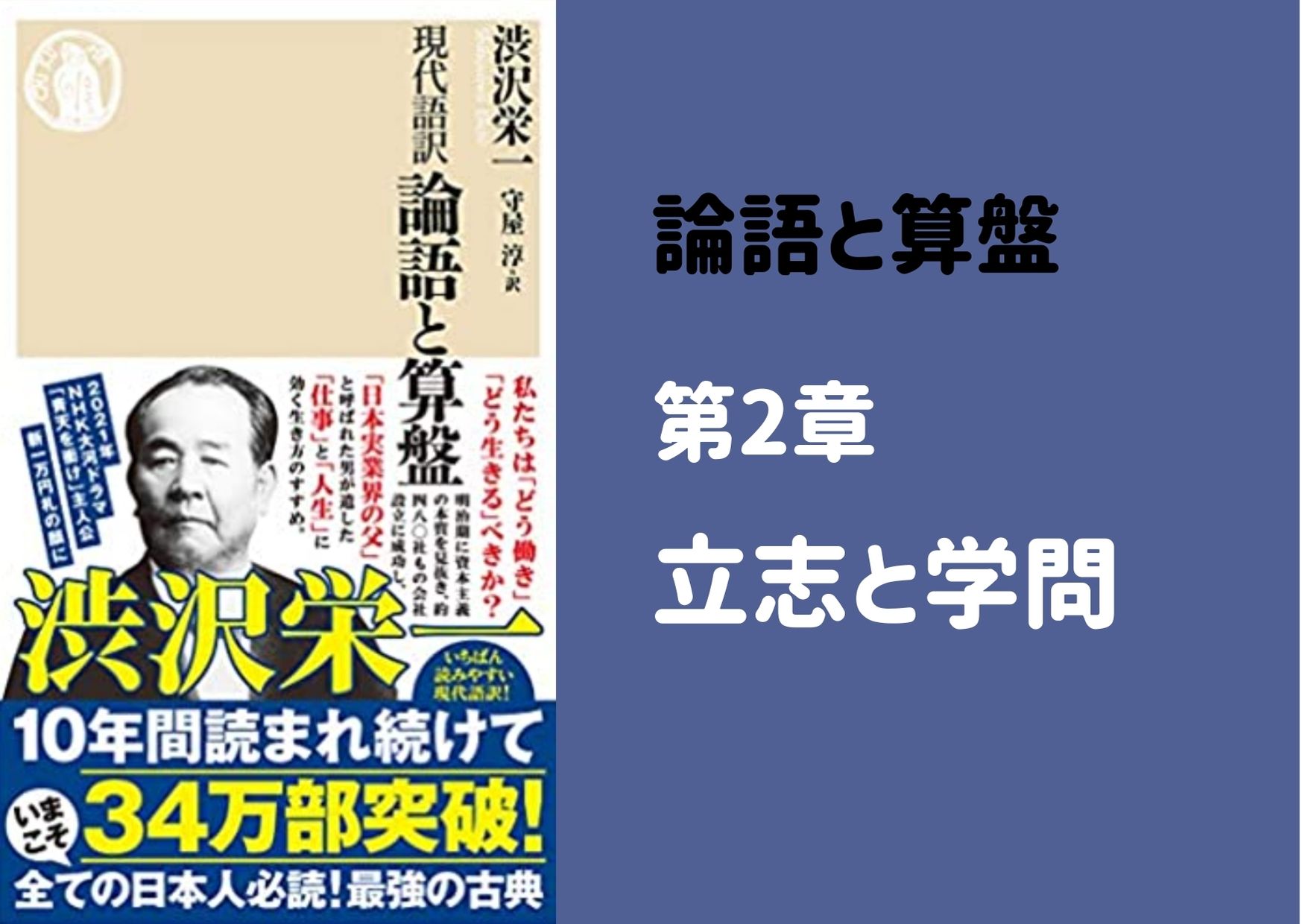
-
渋沢栄一『現代語訳:論語と算盤』第2章「立志と学問」の要約まとめ
続きを見る
渋沢イズムをより深く知りたい方は本書をいちど手に取ってみることをオススメします。
マンガ版も要点が分かりやすくてオススメですよ。
AmazonのオーディオブックAudibleの無料体験で聴くこともできるので、フルで楽しみたい方はどうぞ。
-

-
【聴く読書】Audible(オーディブル)ってどんなサービス?
続きを見る
今回は以上です。